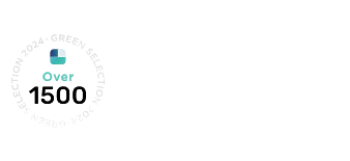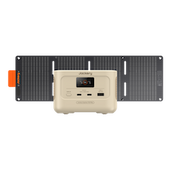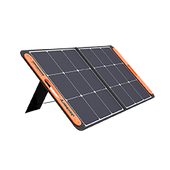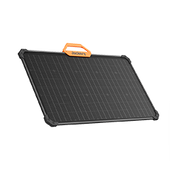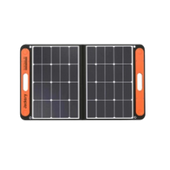1、日本で行われる春の行事といえば
始まりの季節である春。桜の下で楽しむお花見や家族で祝うひな祭り、春分の日や端午の節句など、家族全員で楽しめる行事が目白押しです。日本で行われる春の行事を紹介します。
3月|ひな祭り
ひな祭りとは、女の子の健やかな成長を願って3月3日に行われる日本の伝統行事です。ひな人形を飾る風習は、平安時代の「流し雛」に由来し、紙や藁で作った人形を川に流して災厄を祓う行事が発展しました。
現在では、段飾りのひな人形や、ひなあられ、菱餅、ちらし寿司などが定番です。人形には、子どもたちの身代わりとなって災いを引き受ける意味が込められており、家族の願いと愛情が詰まっています。
3月|ホワイトデー
ホワイトデーは、毎年3月14日に祝われる日本発祥のイベントで、バレンタインデーにチョコレートやプレゼントを受け取った人が、お返しを贈る日です。起源は1970年代後半、福岡の老舗菓子店「石村萬盛堂」がマシュマロをお返しとして提案したことに始まります。
現在ではクッキー、キャンディー、アクセサリーなど多様な贈り物が人気です。お返しには「ありがとう」の気持ちだけでなく、相手への特別な想いを伝える意味も込められています。近年は恋愛関係に限らず、友人や同僚への感謝を示す場としても定着しています。
3月|春分の日
春分の日とは、毎年3月20日頃に訪れる日本の国民の祝日です。「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」として制定されています。春分は昼と夜の長さがほぼ等しくなる日で、これを境に日が徐々に長くなり、本格的な春の訪れを告げます。
もともとは農耕の節目として重要視され、現在では祖先を敬い、お墓参りをする風習も根付いているのが特徴です。春分の日を含む前後7日間は「春のお彼岸」と呼ばれ、ぼたもちを食べる習慣も広く知られています。
3月|卒業式
卒業式は、学校で学び終えた学生がその成果を祝う行事です。卒業式は通常、春に行われ、学生たちは新たなステージへの一歩を踏み出します。小学校、中学校、高校、大学など、それぞれの段階で行われ、卒業証書を授与されるのが特徴です。
学業を修了したことを祝うとともに、これまで支えてくれた家族や教師への感謝の気持ちを表す場でもあります。卒業生は制服や式服を着て、感動的なスピーチや涙ながらの別れが交わされることも多く、成長の証として多くの思い出が刻まれる瞬間です。
3月|春休み
春休みとは、学校教育法で定められる3月下旬から4月の始めにかけての春季休暇です。春休みの期間は各市区町村によって決められているため、公立の小・中・高校で差はほとんどありません。
春休みは学生にとって、1年間の学びを振り返りながら、新しい学年に向けて心身をリフレッシュする期間でもあります。友達や家族と過ごしたり、新しい趣味に挑戦したりと、過ごし方は人によって様々です。
3月|お花見
お花見は、日本の春の風物詩であり、桜の花が満開になる時期に行われる伝統的な春行事です。お花見では、家族や友人、同僚たちと一緒に桜の下でピクニックを楽しむことが一般的で、食事や飲み物を持ち寄りながら、桜の美しさに心を癒されます。
桜の花が短い期間で散ってしまうため、その儚さに対する感慨もお花見の魅力の一つです。日本の春を象徴する行事として、毎年多くの人々が楽しみにしています。
関連記事:花見バーベキューができるおすすめスポットを地域別で紹介
4月|入学式
入学式は、新しい学年に進むための門出を祝う大切な行事です。日本では、4月上旬に多くの学校で入学式が開催され、未来を担う新入生を迎えます。式典では校長の祝辞や新入生代表の挨拶が行われ、入学の喜びと期待が共有されます。
入学式の後には、保護者と一緒に「入学式」の看板前で記念写真を撮るのが定番です。子供は教室へと移動し、先生の話を聞いて配布物を受け取ります。
4月|エイプリルフール
エイプリルフールは、毎年4月1日に行われる、ユーモアを交えた嘘や冗談を楽しむ日です。人々が軽い嘘をついて他人を驚かせたり、ジョークを楽しんだりします。世界中で広く認知されており、企業がユニークなジョークを披露する場面に遭遇した方も多いでしょう。
エイプリルフールの起源は諸説ありますが、14世紀のフランスで新年を1月1日ではなく、4月1日として祝っていたのが始まりという説もあります。エイプリルフールでは、人を精神的・肉体的・経済的に苦しめないという前提で、嘘を披露します。
4月|イースター
イースターはキリスト教における最も重要な祭りのひとつで、イエス・キリストの復活を祝う日です。毎年春に行われ、日付は春分の日後の最初の満月の次の日曜日に決まります。
イースターは、キリストの死と復活の意味を深く考え、信仰を新たにする日として位置付けられています。最近では、宗教的な意味合いに加えて、家族で集まり、食事やエッグハントを楽しむ文化的な行事としても親しまれているのが特徴です。
5月|GW(ゴールデンウィーク)
ゴールデンウィークとは、4月末から5月上旬にかけての国民の祝日です。4つの祝日が続くため、全国は旅行客で溢れかえります。ゴールデンウィーク期間中は、様々な企業や飲食店、ショップなどが独自のセールを開催しているのも特徴です。
ただし、ゴールデンウィーク期間中には、以下のようなデメリットも存在します。
● 宿泊施設の予約が取りづらい
● 宿泊施設や航空券の料金が高くなる
● 観光施設は混雑している
関連記事:ゴールデンウィーク(GW)のお出かけスポット12選【地域別】!+キャンプのススメ
5月|こどもの日(端午の節句)
こどもの日(端午の節句)は、5月5日に祝われる日本伝統の春行事です。こどもの日は男女関係なく、子供の健康と成長を願います。一方、端午の節句は、男の子の成長をお祝いする行事です。もともと中国から伝わった端午の祭りが日本に取り入れられました。
こどもの日には、鯉のぼりや鎧兜を飾ったり、菖蒲湯に入ったりします。地域ごとに異なるイベントや行事が行われているので、こどもの日ならではの楽しみ方が広がります。
5月|母の日
母の日は、毎年5月の第2日曜日に祝われる、母親への感謝の気持ちを伝える行事です。母親に花や贈り物を贈ったり、食事を共にしたりと思い思いの方法で感謝を伝えます。母の日は、アメリカから伝わった習慣で、最初は亡くなった母親を偲ぶ日として始まりました。
次第に現在のような感謝を表現する日へと変化し、日本でも日頃の感謝の気持ちを込めて、母親に特別なプレゼントを贈る習慣が根付いています。家族や兄弟と相談して、サプライズプレゼントを計画してみてはいかがですか。
関連記事:高齢者に喜ばれるプレゼント11選!健康グッズや食べ物のおすすめも厳選
2.【日本の伝統】春行事の食べ物メニュー3選

春は、日本の文化や風習を感じる行事が盛りだくさんです。そんな春の行事に欠かせないのが、季節感あふれる伝統的な行事食です。春の味覚が詰まった行事食メニューは、春の訪れを感じさせてくれます。日本の伝統的な春の行事食メニューは、以下のとおりです。
①桃の節句|ちらし寿司・菱餅・白酒
3月3日の桃の節句は、女の子の健やかな成長を願う大切な行事です。桃の節句には、色鮮やかな「ちらし寿司」が食卓を飾り、見た目にも華やかで春の訪れを感じさせてくれます。
「菱餅」は、緑・白・ピンクの三色で新緑・純白の雪・桃の花を表現しています。ひなまつりの歌の中にも登場する「白酒」は、蒸した白米と米麹を混ぜ合わせたものに酒を加えて熟成させ、石臼でひいて造るお酒です。
②春の彼岸|ぼたもち
春の彼岸は、春分の日を中心とした7日間で、先祖を供養する日本の伝統行事です。春の彼岸に欠かせない「ぼたもち」は、春に咲く牡丹の花にちなんで名付けられたお菓子。
もち米とあんこで作られたぼたもちは、昔から魔除けや豊作祈願の意味も込められ、供え物として親しまれてきました。昔は砂糖が貴重な調味料だったので、砂糖を使うぼたもちを先祖にお供えすることで、感謝の気持ちを伝えています。
③端午の節句|柏餅・ちまき
5月5日の端午の節句は、男の子の健やかな成長と立身出世を願う日本の伝統行事です。縁起の良い行事食として「柏餅」と「ちまき」が親しまれています。柏の木は、新しい芽が出ないと古い葉が落ちないため、子孫繁栄につなげられています。
ちまきは、端午の節句と一緒に中国から伝えられたのが日本における起源です。厄除けの力があるとされる笹の葉で包まれ、子どもを災いから守る願いが込められています。
関連記事:お花見弁当の定番レシピ20選!花見で温かい料理を作る裏ワザも解説
3.【地域別】春の伝統行事・イベント5選
全国では、その土地ならではの文化や歴史を感じられる貴重な春の行事が開催されます。普段とは異なる春の行事を楽しみたい方は、ぜひ地域のイベントに参加してみてください。各地域で開催される春の伝統行事は、以下のとおりです。
大阪|菜種御供大祭

菅原道真公の命日である毎年3月25日に明寺天満宮で開催される春行事。神前に菜の花とクチナシの実で黄色く染めた団子が供えられ、景品付菜種御供授与や稚児行列が行われます。
神社がある大阪の河内地方では、河内の春ごとと呼ばれて親しまれているのが特徴です。。お供えした団子は病気平癒のご利益があるとされ、24日〜26日の期間中であれば、誰でも授かれます。
奈良|お水取り

東大寺で開催される伝統行事「お水取り」は、新暦3月1日〜14日の2週間にわたり、11人で行われる悔過法要です。悔過とは、仏・法・僧の三宝に向かい、己の罪を認めて悔い改める行を指します。
旧年中の懺悔を行うとともに、新年の利益を得る法要を行います。お水取りは、西暦752年から現在まで欠かさずに執り行われてきた行事です。2025年のお水取りでは、1274回目を迎えます。
広島|鞆の浦観光鯛網

約380年の伝統がある「鞆の浦の鯛網」は、伝統漁法で鯛を追い込む行事です。出船前には、鞆の浦アイヤ節保存会の踊り手がアイヤ節を披露します。その後、乙姫様が船上で「弁天龍宮の舞」を華麗に舞い、出船の合図です。
観光客は遊覧フェリーに乗船し、鯛網船団を後ろから見守ります。網入れ後に網を素早く引き上げると、真鯛が大漁です。観光客は獲れたての真鯛をその場で購入できます。
京都|豊太閤花見行列

1598年に太閤秀吉が「醍醐の花見」を行ったことにならい、毎年4月第二日曜日に開催される豊太閤花見行列。秀吉公・北政所・淀殿らに扮した行列が境内を練り歩きます。
醍醐寺は、平安時代から「花の醍醐」と言われるほどの桜の名所です。枝垂れ桜や染井吉野、山桜、八重桜など、数多くの桜の下でお花見を楽しめます。
福岡|博多どんたく

1179年に始まったとされる伝統的な民俗行事です。毎年、国内外から200万人以上の人が訪れ、福岡の街は活気に溢れます。馬に乗った三福神が、2日間で150カ所以上もの商家や企業をお祝いして廻ります。
博多どんたくは前夜祭から始まり、式典・マーチング・どんたく広場パレードなど、様々なイベントが開催されるのが特徴です。フィナーレの総踊りでは、みんなで盛り上がれます。
4.Jackeryポータブル電源で春のアウトドアをもっと快適に!
春休みやゴールデンウィーク、お花見などの春の行事では、ポータブル電源が大活躍します。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を蓄え、コンセントがない場所でも電化製品を動かせる機器です。春の行事にポータブル電源を持参するメリットは、以下のとおりです。
● 電気ストーブや電気毛布などの暖房機器を使い、アウトドアでも快適な気温で過ごせる
● 電子レンジや電気ケトルを使い、簡単に行事食を作れる
● ポータブル冷蔵庫にアウトドアで作る料理の食材を冷蔵保存しておける
● LEDランタンを点灯させて、夜の暗闇を照らせる
● 行事の情報を調べるためのスマホを、常にフル充電にしておける
アウトドアで使用するポータブル電源は、創業から13年間で世界販売台数500万台を突破した実績を誇るJackery(ジャクリ)がおすすめです。業界最大級の軽量コンパクト設計を誇るので、屋外へ気軽に持ち運べます。
耐振動性や耐久性、耐火性などに優れているため、屋外で使用しても故障する心配はありません。ソーラーパネルと併用すれば、屋外にいながら太陽光発電で繰り返し充電も可能のため、連泊キャンプや長期の車中泊も安心。
キャンプに革命を。Jackeryのポータブル電源で広がる自由
まとめ
春には、ひな祭りやお花見、春分の日、子どもの日などの様々な行事があります。春の行事食も揃えれば、本格的に行事が楽しめるでしょう。地域に根付いた行事も開催されているので、地方に足を運んで普段と異なる春を体験してみるのもおすすめです。
この記事で紹介した春の行事を通して、日本の歴史を感じてみてください。