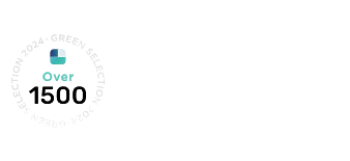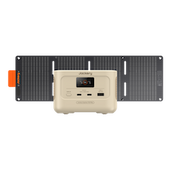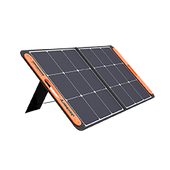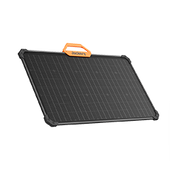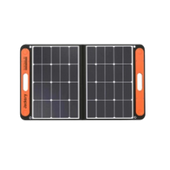1.防災士は自然災害から命や生活を守るための専門資格を持つ人
防災士は自然災害から人々の命や生活を守るために必要な知識と技術を身につけた防災の専門家です。
ここからは、防災士がどういう資格なのか、取得に必要な条件を詳しく解説していきます。費用についても解説しているので、資格取得の参考にしてください。
●日本防災士機構が認証する民間資格
防災士は日本防災士機構が認証する民間資格で、2024年11月末日に累計30万人を突破しました。この資格は台風や地震など災害に備える知識と技術を証明するもので、取得するには講座の受講や実技訓練などを修了する必要があります。
参考:日本防災士機構
資格を取得した防災士は自治体や地域住民と協力し、災害発生時の救助活動や復旧支援などで活躍することを期待されています。
関連人気記事:防災士という資格を知っていますか?
●資格取得に必要な条件や費用
防災士の資格を取得するには、以下のような条件を満たす必要があります。
・防災士養成講座の受講
・実技講習の修了
・資格認定試験の合格
・申請手続きと認定費用の支払い
これらの条件を満たして防災士として認定されると、地域の防災活動を支える専門家として活動できるようになります。
また防災士の資格を取得するには、「講座受講料・教材費・実技講習費・試験料・認定登録料」を含めて総額10万円前後の費用が必要です。
具体的な金額は受講する講座の運営団体や地域によって異なるため、防災士の資格を取りたいと考えている方は事前に問い合わせてみましょう。
●防災士の資格を取る手順と内容
防災士の資格を得る手順と内容は、以下のようになっています。
|
資格取得の流れ |
内容 |
|
1.防災士養成講座を受講する |
災害に関する基礎知識や対応方法、地域防災の重要性について学ぶ。講義形式で行われる。 |
|
2.実技講習を受講する |
心肺蘇生法やAEDの使用方法、応急手当など災害現場で必要となる実践的なスキルを訓練する。 |
|
3.資格認定試験を受験する |
防災に関する知識を問う試験。講座内容をもとに出題される。 |
|
4.資格認定申請と登録を行う |
試験に合格後、日本防災士機構に資格認定を申請する。認定には所定の登録料を払う必要がある。 |
講座の受講や実技講習は、防災士の資格を取得するためには欠かせないステップです。ここでしっかりと自然災害や対応方法などについて学び、その知識を試験で発揮して資格の取得を目指しましょう。
●防災士の主な役割
防災士は、以下のようにさまざまな場面での活躍を期待されています。
・防災教育や啓発運動
・災害発生時の対応
・避難所運営のサポート
・地域防災計画への参加
・災害復旧や復興支援
防災士は専門知識と実践的なスキルを活かし、平時から災害発生後まで一貫して地域を支える活動をしています。
2.防災士が役に立たないと言われている理由5選
防災の専門家である防災士ですが、「役に立たない」と言われることも少なくありません。
なぜ役に立たないと言われているのか、その原因を見ていきましょう。
①民間資格なので法的権限がない
防災士は日本防災士機構が認定する民間の試験なので、公的資格ではありません。そのため活動に法的な権限が伴わず、災害時の現場で強制力を持った指示を出すことができないのです。
法的権限がないことでその役割や価値が十分に理解されないこともあり、「防災士は役に立たない」と言われてしまっています。
②実務における対応力が不足する場合がある
防災士は理論や知識を学ぶことが中心の資格なので、実務で求められる現場対応力が不足していると指摘されています。災害時には瞬時の判断力や迅速な対応が求められる場面が多く、講座で学んだ内容だけでは十分に対応できないことがあるのです。
また実際に現場で指導的な立場を取るためには、周囲との調整や指示といった円滑なコミュニケーションスキルも求められます。これらのスキルが不足していると、災害時にその対応力が発揮されにくい場合があるようです。
③防災士の役割や重要性が理解されていない
防災士が「役に立たない」と言われる理由の1つに、その役割や重要性が十分に理解されていないことがあります。とくに一般の人々や地域の行政は、防災士の業務内容や役割を把握していないことが多いです。
さらに、防災士が行う防災教育や啓発活動は長期的な視点で効果を発揮するため、即効性を期待する人々にとっては、その効果を実感しづらいことも原因となっています。
④災害の規模によって対応に限界がある
災害の規模によって対応能力に限界があることも、防災士が「役に立たない」と言われる理由の1つです。防災士は地域レベルでの防災活動や支援が主な任務なため、大規模な災害が発生した場合に活動範囲やリソースに制約が生じることがあるのです。
また大規模災害時には防災士はあくまでサポート的な役割を担うことになってしまうことも、「役に立たない」と感じさせる要因となっています。
⑤活動の機会が少ない
防災士が「役に立たない」と言われているのは、実際に活動する機会が少ないことも原因にあげられます。防災士は主に災害発生時に活動するため、資格を取得しても日常生活でそのスキルを活かせず、資格の有用性が実感しにくくなっているようです。
3.【役に立たない?】防災士資格を取得する3つのメリット
ここまで見てきたように「防災士は役に立たない」と考えられがちですが、資格を取得すると以下3つメリットがあります。
・防災に関する正しい知識が身につく
・災害対応のリーダーとして信頼されやすい
・地域や職場の防災訓練に貢献できる
それぞれ詳しく、解説していきます。
①防災に関する正しい知識が身につく
防災士資格を取得する最大のメリットは、防災に関する正しい知識を学べることです。
防災士養成講座では、防災に関する基礎知識から心肺蘇生法や応急手当など実践で役立つ技術を学ぶことできます。
防災士として学んだ知識は災害の予防や発生時の対応に加え、復興支援や地域防災活動にも役立つので社会全体の安全性を高めることにも貢献できます。
②災害対応のリーダーとして信頼されやすい
防災士は災害時の迅速な判断力や適切な対応が求められる場面で、専門的な知識とスキルによって周囲から頼りにされる存在となります。
災害時においてリーダーとして信頼を得やすくなり、「社会貢献ができた」という達成感をを得ることができるでしょう。
③地域や職場の防災訓練に貢献できる
防災士資格を取得すると、地域や職場の防災訓練に積極的に貢献できることもメリットの1つです。防災士は災害時の行動計画や応急手当など実際の対応に必要な知識とスキルを活かし、防災訓練の企画・実施のサポートが可能になります。防災訓練で適切な指導を行うことで信頼を得ながら、地域や職場の防災意識を向上させられるでしょう。
関連人気記事:防災士の資格を取得する3つのメリット!取り方・費用や就職先も解説
4.防災士以外の防災関連資格3選

防災に関連する資格は、防災士以外にも以下の3つが存在します。
・救命救急士
・防災管理者
・防災危機管理者
ここからは、防災士以外の防災関連資格を3つご紹介していきます。
①救急救命士
救命救急士は、緊急時における命を守るための救急医療処置を行う専門職です。主に病院や救急車で活動しており、心肺停止や重傷を負った患者に対して、医師の指示を受け応急処置を行う役割を担っています。
災害時に、他の防災関連資格と協力しながら救助活動や支援活動を行う貴重な存在と言えるでしょう。
②防災管理者
防災管理者は、企業や団体における防災活動の計画・実施・管理を担当する専門職です。職場や施設における防災計画や、従業員の防災訓練の実施、災害発生時の対応指針の確立など、広範な防災業務を主に担当しています。
とくに企業や工場・学校・公共施設などで従業員や生徒の安全を確保する役割を果たしており、労働安全衛生法や消防法などに基づき設置義務のある職種として位置づけられている場合もあります。
③防災危機管理者
防災危機管理者は企業や自治体、公共機関などで災害やテロ、大規模事故などの危機的状況に対する総合的な危機管理計画を策定・実行する専門職です。
災害が発生した際に迅速かつ効果的に対応するための準備を整え、組織全体の危機対応能力を高める役割を担っています。
5.災害時の停電対策に!Jackeryポータブル電源で防災を万全に
災害時に発生しやすい停電は、私たちの生活に大きな影響を与えます。とくにスマホやラジオといった情報収集手段や照明、冷暖房が使えなくなると命に関わる事態になりかねません。
こうした災害時の停電対策として注目されているのが、モバイルバッテリーよりも大容量で家電に給電できる持ち運びにも便利なJackery(ジャクリ)のポータブル電源です。
【Jackery(ジャクリ)ポータブル電源のおすすめポイント】
・扇風機や電気毛布などの冷暖房が使用できるから停電時の暑さ・寒さ対策ができる
・電気ケトルなどの調理家電を使用して災害時にも温かい料理が食べられる
・防災安全協会に認められるほど安全性が高く、静音設計だから避難先でも安心して使用できる
・ソーラーパネル対応だから停電が長期化しても繰り返し充電して使用できる
・防災対策としてだけでなく、キャンプなどのアウトドアや普段使いの節電にも活躍する
USBとACコンセントを同時に搭載しているのでスマホの充電だけでなく、テレビや電子レンジ、電気毛布などの家電も災害時に使用できます。
内蔵バッテリーには最新のリン酸リチウムイオン電池を採用。毎日使用しても10年以上使い続けることができ、コスパに優れているところも魅力です。
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源を導入してキャンプや車中泊などのアウトドアを楽しみながら、いつ起こるかわからない災害に備えましょう。
関連人気記事:ポータブル電源は防災に必要?災害時の使い方と事前の準備をご紹介
もっと多くの商品を見る
6.防災士に関するよくある質問
ここからは、防災士に関するよくある質問にお答えしていきます。
●防災危機管理者と防災士の違いはなんですか?
防災危機管理者と防災士は、どちらも防災に関わる資格ですが、役割や目的、対象とする分野にいくつかの違いがあります。
|
項目 |
防災危機管理者 |
防災士 |
|
主な活動対象 |
企業や組織 |
地域社会や個人 |
|
目的 |
組織の危機管理体制を強化 |
地域社会や個人の 防災力向上 |
|
対象リスク |
自然災害+事故 テロなど広範囲 |
自然災害が中心 |
|
資格の取得方法 |
専門講習と試験 |
養成講座と試験 |
|
主な活動範囲 |
防災計画やBCPの 策定・運用 |
地域防災 |
防災危機管理者が組織を対象としているのに対し、防災士は地域や個人を対象としています。どちらの資格を取るか悩んでいるなら、自分の目的や活動範囲に合う方を選択しましょう。
●防災士が国家資格化される予定はありますか?
現時点では、防災士が国家資格化される予定は公表されていません。国家資格化の動きがある場合、日本防災士機構や関連機関から正式な発表が行われるでしょう。
●防災士資格は更新が必要ですか?
防災士資格の更新は必要ありません。防災士資格は有効期限がなく、一度取得すれば生涯有効です。
ただし、知識や技術を維持・向上させるために定期的な研修や訓練に参加することが推奨されています。迅速で適切な対応を取るには最新の防災知識が必要不可欠となるため、研修や訓練には積極的に参加していきましょう。
●防災士の活動で給料は出ますか?
防災士の活動がボランティアの場合は、給料は出ません。一方で自治体や企業の防災担当として活動を行う場合は、給料が支払われます。
●防災士の資格を持つと就職に有利になりますか?
防災士の資格を持つと、以下のような災害対策に関わる職種や業界での就職に有利になることがあります。
・自治体や公共機関
・企業の防災関連部門
・学校や医療機関、福祉施設
・防災関連の専門職
とくに防災関連の業務や危機管理の部署に就職を希望する場合は、資格が大きな強みになるでしょう。
まとめ
防災士は自然災害から命や生活を守るための資格で、地域や職場の防災訓練に貢献できます。資格を取得することで、まわりの人の防災意識を高めるきっかけを作っていきましょう。
防災意識を高めるなら日頃から災害に備えておくのもポイントです。Jackery(ジャクリ)のポータブル電源を導入して、停電が発生しても慌てず冷静に過ごせるように備えましょう。