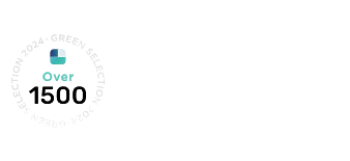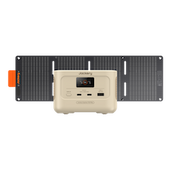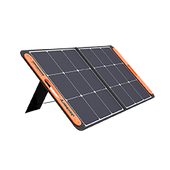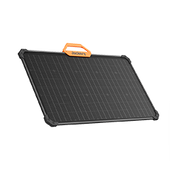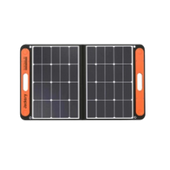1.小学校で避難訓練が行われている理由は?
小学校で避難訓練を行っている最大の理由は、「児童の命を守るため」です。地震や火災、津波など学校で起こりうる緊急事態でも、落ち着いて避難できるように訓練を行っています。
小学校の避難訓練が何を基準・目安にして行われているのか、次で詳しく見ていきましょう。
●小学校での避難訓練は義務
小学校では、児童の安全を守るために避難訓練の実施が義務付けられています。これは日本の学校保健安全法や防災基本計画などの法律・指針に基づくもので、各学校は災害や緊急時に備えた訓練を計画的に実施しなければなりません。
避難訓練は、子どもたちの安全を守るために必要不可欠な取り組みです。保護者もその重要性を理解し、家庭での防災対策と連携させていきましょう。
●小学校の避難訓練は危機管理マニュアルに基づいて行われている
小学校の避難訓練は、「危機管理マニュアル」に基づいて実施されています。このマニュアルは、災害や緊急事態が発生した際に学校がどのように対応すべきか詳細に記載されているもの。各学校はこれを元に事前に計画を立てていきます。
マニュアルの手順に従った避難訓練で、実際に災害が発生した際に児童たちが落ち着いた行動を取れるように指導しているのです。
●小学校の避難訓練は緊急放送から5分以内の避難を目安とされている
小学校の避難訓練は、緊急放送が流れてから「5分以内に避難を完了すること」を目安に実施しています。この目標は、災害発生時に迅速に避難行動を起こすために設定された、児童が混乱せずに安全な場所へ避難するための工夫です。
この目標を達成することで災害時の初動対応の迅速さが確保され、児童の安全が守られています。
●東京都の小学校では年に11回以上実施している
小学校での避難訓練の実施回数は地域や学校によって異なりますが、一般的には「年間6回〜12回程度」の実施が推奨されています。
例えば東京都の公立小学校では、「年間11回以上」の避難訓練が義務付けられています。地震や火災、不審者対応などさまざまな状況に応じた訓練を繰り返すことで、児童が素早く安全に行動する力を養っているのです。
参考:年度当初における幼児・児童・生徒の安全指導の徹底について
関連人気記事:保育園での避難訓練のやり方【5ステップ】子どもへ地震を伝える3つの方法
2.小学校で避難訓練を行う2つの目的と合言葉

小学校で避難訓練を行う目的は、大きく分けて児童の安全確保と教職員の対応力向上の2つです。ここからは、小学校で避難訓練を行う2つの目的と合言葉について詳しく解説していきます。
●緊急時に児童が適切な行動を取れるように指導する
避難訓練の重要な目的の1つは、児童が緊急時に適切な行動を取れるよう指導することです。
地震や火災、津波、不審者の侵入など、起こりうる緊急事態を想定し、いざというときに冷静に避難できるように訓練を通じて具体的な行動を学んでいきます。
訓練を繰り返し行い、児童が自分で身を守る方法を自然と覚えられるように工夫されているのです。
●緊急時に教職員が迅速かつ安全に児童を避難させる手順を確認する
避難訓練では、児童だけでなく教職員の対応力を高めることも目的としています。
災害や緊急事態が発生した際、教職員は児童を安全に避難させる責任を担います。訓練を通じて避難誘導の手順や指示の出し方を確認することで、冷静で的確な対応が素早くできるように準備を整えているのです。
また、災害の種類によって避難方法が異なるため、状況ごとに適切な指示が出せるように訓練しています。
●避難時の合言葉は「おはしもて」
小学校の避難訓練では、児童が安全に避難できるよう「おはしもて」という合言葉を使って指導しています。これは、以下のような避難時に守るべき基本的なルールを簡単に覚えられるようにしたものです。
・お:押さない
・は:走らない
・し:しゃべらない
・も:戻らない
・て:低学年優先
この合言葉によって児童は避難時にどう行動すればいいかを理解し、実際の災害時にも落ち着いて安全に避難できるようになっていきます。
3.小学校で行われる避難訓練の内容
小学校では、以下の4つの状況に合わせた避難訓練を行っています。
・火災
・地震
・不審者
・津波
それぞれ詳しく解説していきます。
●火災避難訓練
「火災避難訓練」は、学校で火災が発生した際に児童が安全に避難できるよう備えるための訓練です。
火災避難訓練では、「姿勢を低くしてハンカチや袖で口と鼻を覆いながら避難する」ことを徹底して訓練を行います。これは、煙を吸い込むと一酸化炭素中毒の危険があるためです。
また火災報知器が鳴った際の行動や、非常口・避難経路も確認もすることで実際の火災時に冷静に対応できるよう準備しています。
●地震避難訓練
「地震避難訓練」は、地震発生時に児童が素早く身を守り、安全に避難するための訓練です。地震は揺れによる転倒や落下物から身を守るために、以下を欠かさずに行います。
・姿勢を低くする
・机の下に隠れる
・頭を守る
その後、揺れが収まったことを確認したら、教職員の指示に従って避難を開始。実際の地震発生時にも冷静に行動し、素早く避難する力を養っていきます。
●不審者対応訓練
「不審者対応訓練」は、学校内や周辺で不審者が発生した際に児童と教職員が安全を確保するための訓練です。近年、不審者による事件が増えており、学校でも危機管理の強化が求められています。
児童はこの訓練で不審者に遭遇した際の適切な行動として、以下のルールを学びます。
・近づかない
・すぐに大人に知らせる
・安全な場所に避難する
また、教室内にいる場合にはドアや窓を施錠するなど具体的な対応を実践し、児童が自分で身を守る術を身につけています。
●津波避難訓練
「津波避難訓練」は、地震発生後に津波が発生する可能性がある際に迅速かつ安全に高台や指定避難場所へ避難するための訓練です。とくに、海沿いの地域では重要な防災対策の1つとされています。
津波は地震発生後、数分~数十分で襲来する可能性があるため、時間を意識して迅速に行動する訓練を行っています。
4.小学校で行われる避難訓練の流れ

小学校で行われる避難訓練は、以下の流れにそって行われています。
1.事前準備をする
2.非常ベルや緊急放送が流れる
3.安全確保を行う
4.指示に従って安全な場所へ避難する
5.避難が完了したら安全確認と点呼を行う
それぞれ詳しくみていきましょう。
①事前準備をする
避難訓練を効果的に行うためには、事前準備が欠かせません。訓練の目的を明確にし、児童・教職員がスムーズに行動できるよう準備を整えていきます。
具体的に行なっている準備は、以下のとおりです。
・避難訓練の計画を作成し
・訓練の種類や想定される状況を決定する
・避難経路を決定する
・緊急放送の内容を確認する
・避難誘導の流れを事前に共有する
事前準備をしっかり行うことで訓練の効果が高まり、実際の災害時にも冷静に対応できる力を身につけることへとつながります。
②非常ベルや緊急放送が流れる
避難訓練が始まると最初に非常ベルや緊急放送が流れ、訓練の開始を知らせます。これは、災害時に子どもたちがすぐに避難行動を取るための合図です。
非常ベルや緊急放送の音は実際の災害時にも同じように使用されるため、児童や教職員はこの音を聞くことで即座に避難が必要であることを認識します。
非常ベルや緊急放送を訓練の中で経験することで、実際に災害が発生したときにも児童は混乱せずスムーズに避難行動を取れるようになるのです。
③安全確保を行う
災害時にもっとも優先すべきなのは、安全を確保することです。安全確保の方法は、発生した災害が地震か火災かによって以下のように異なります。
・地震の場合:落下物、転倒の恐れがあるものや移動してくる可能性があるものから離れる
・火災の場合:口元をハンカチや袖口で覆い、煙を吸い込まないように身をかがめる
各災害に応じた初動対応をもとに教職員は周囲の状況を確認しながら誘導し、子どもたちを安全に避難させています。
④指示に従って安全な場所へ避難する
非常ベルや緊急放送が鳴り、初動対応を行った後は、教職員の指示のもと安全な場所へ避難します。避難時には「おはしもて」のルールを守り、落ち着いて行動するのがポイントです。
実際に災害が起こった際に途中で押し合ったり、走ったりしないよう一人ひとりが冷静に移動できるように訓練します。
また、避難途中で出口が塞がれている場合は別のルートで避難するなど、想定外の事態にも適切に対応できるよう訓練を行うことも大切です。
⑤避難が完了したら安全確認と点呼を行う
避難場所に到着したら、児童全員の安全確認と点呼を行います。これは、避難中に取り残された児童がいないか、体調不良やケガをした児童がいないかを把握するためです。
異変があればすぐに報告し、適切な対応が取れるようにしていきます。
こうした流れで訓練を行うことで、実際の災害時にも落ち着いて対応できる力を養い、安全に避難するための力を身につけていくのです。
関連人気記事:【保護者向け】引き渡し訓練のねらい・流れや防災の備えを徹底解説
5.避難訓練をきっかけに防災意識を高めよう!家庭でできる取り組み3選

学校での避難訓練は、児童が災害時に適切な行動を取れるようになるための大切な学びの場です。しかし、防災は学校だけでなく、家庭でも意識を高めて備えておく必要があります。
ここでは、防災意識を高めるために家庭でもできる3つの取り組みについて解説します。避難訓練をきっかけに、家庭での防災意識を見直してみましょう。
●家族で避難計画を立てる:避難ルート・避難場所・緊急連絡先の確認と共有
災害はいつどこで起こるかわかりません。自宅にいるときだけでなく、家族が別々の場所にいる場合でも安全に避難できるよう、事前に避難計画を立てておきましょう。
避難ルートは地震や火災、洪水などの災害ごとに最適な避難経路や避難場所が異なるため、ハザードマップを活用して複数考えておくと安心です。
また携帯電話が使えない状況を想定し、公衆電話の使い方や「災害用伝言ダイヤル(171)」の利用方法を家族で確認しておきましょう。
●非常用持ち出しバッグを準備する:子ども用のものを自分で用意させよう
災害時にすぐに避難できるよう、非常用持ち出しバッグを準備しておきましょう。とくに子どもがいる家庭では、大人用の非常バッグとは別に子ども用も用意しておくと安心です。
【子ども用持ち出しバッグに入れておきたいもの】
・飲み物、軽食
・ハンカチ、タオル、ティッシュ
・懐中電灯(小型で軽いもの)
・防寒用のブランケットやレインウェア
・家族の連絡先を書いたメモ
・ホイッスル(助けを呼ぶ用)
子ども用持ち出しバッグは、防災意識を高めるために子どもたち自身で準備させるのがポイントです。
●備蓄や防災グッズの準備・確認:非常食・懐中電灯・ポータブル電源など
災害時にはライフラインが止まり、電気・水道・ガスが使えなくなる可能性があります。そのため、以下のような備蓄や防災グッズの準備が不可欠です。
・非常食・飲料水(1人あたり1日3Lが目安で3〜1週間分)
・懐中電灯・ランタン
・ポータブル電源
・救急セット・常備薬(持病のある人はとくに重要)
・防寒・雨具
・携帯ラジオ
家族で「何が必要か」「どこに保管しているか」を話し合い、定期的に見直すことで災害時に落ち着いて行動できるように備えましょう。
6.非常時にも安心を!Jackeryポータブル電源で災害停電対策を万全に!
災害時に停電が発生すると照明や暖房が使えなくなったり、生活に大きな支障が出る可能性があります。とくに小さな子どもがいる家庭では、安心して過ごせる環境を確保するため「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源を用意しましょう。
「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源が非常用電源として優れている理由は、以下のとおりです。
・スマホの充電ができるから連絡手段や最新の災害情報が途切れない
・軽量でコンパクトな設計だから緊急時にサッと持ち運べる
・冷暖房器具の使用や照明の確保ができるから災害時も安心できる環境を作れる
・過充電・過放電を防ぐ保護機能付きだから子どもがいても安心して使える
・ソーラーパネル対応だから停電が長期化しても繰り返し使用できる
不安やストレスを感じやすい災害時だからこそ、「Jackery」のポータブル電源で子どもたちが安心して過ごせる環境を作ってあげましょう。
もっと多くの商品を見る
7.小学校の避難訓練に関するよくある質問
ここからは、小学校の避難訓練に関するよくある質問について解説していきます。
●小学校の避難訓練は年に何回ありますか?
小学校の避難訓練の実施回数は自治体や学校によって異なりますが、一般的に毎年「3〜6回程度」実施されることが多いです。
例えば、東京都の公立小学校では年に11回以上の避難訓練を行うことが義務付けられています。
お子さんの通う小学校での具体的な実施回数は、学校の年間予定表や学校便りで確認するのがおすすめです。
●小学校の避難訓練に保護者は参加できますか?
小学校の避難訓練に保護者が参加できるかどうかは、学校や自治体の方針によって異なります。一般的に、通常の避難訓練には児童と教職員のみが参加することが多いです。
保護者が参加できる避難訓練には、以下のようなものがあります。
・引き渡し訓練
・地域防災訓練
・防災講習会や説明会
避難訓練への参加の可否については、学校の年間行事予定や配布されるお知らせを確認してみてください。
●天候が悪いときの避難訓練はどうなりますか?
天気が悪いときの避難訓練は雨や風の強さ、気温などを考慮して対応が決まります。小雨や少しの風であれば、予定通り実施する学校が多いです。
大雨や強風、雷が予想される場合は屋内での訓練に変更されることがあります。例えば、地震の避難訓練で机の下に隠れたあとに廊下へ出るまでの流れを訓練するなど、室内でできる範囲で実施されるケースもあります。
まとめ
小学校で行われる避難訓練は、子どもたちの防災意識の向上や災害時に正しい行動を取るための取り組みです。学校で取り組んでいるからとそのままにはせず、避難訓練をきっかけに家庭でも防災意識を高めていきましょう。
家庭の防災対策グッズには、「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源がおすすめです。照明の確保や暑さ・寒さ対策、スマホの充電など災害時に心強い「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源で家族の安全を守りましょう。