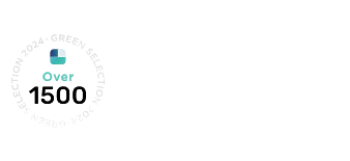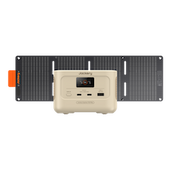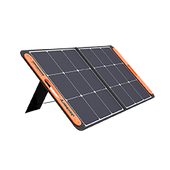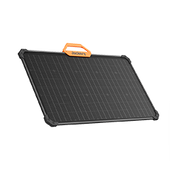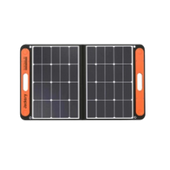1.災害サイクルとは災害発生から次の災害までを期間ごとに分ける考え方

災害サイクルは、災害後の状況を時間経過に応じて5つのフェーズに分けています。
|
フェーズ名 |
期間 |
|
超急性期 |
災害発生から2~3日間 |
|
急性期 |
災害発生から1週間 |
|
亜急性期 |
災害発生から2~3週間 |
|
慢性期 |
災害発生から数か月~数年 |
|
平穏期(※) |
災害による影響がない期間 |
※「平穏期」は「静穏期」とも呼ばれますが、この記事では「平穏期」で統一しています。
災害サイクルとは、災害が発生した直後の「超急性期」から、次の災害に備える「平穏期」までの時間経過を一連の流れとして捉えたものです。災害現場では、各フェーズでの被害状況や復旧の進み具合に応じた医療や看護が求められます。そのため、適切な対応を行うには、災害サイクルの特性を理解し、柔軟に対応しなければいけません。
2.災害サイクルごとに予想される被害・復旧状況
災害現場では、時間の経過とともに被害や復旧の状況が変わります。災害サイクルを理解し、それぞれのフェーズで予想される状況を把握しておくことで、迅速かつ適切な医療・看護活動が可能になります。ここでは、災害サイクルの各フェーズでの被害と復旧状況について詳しく解説します。
●超急性期の状況|災害規模により建物の倒壊・土砂崩れなどの被害
超急性期では、災害の直後に発生する建物の倒壊や土砂崩れなど、広範囲にわたる被害が予想されます。この時期、現場は逃げ惑う人々や避難者の混乱により、非常に緊迫した状況になるでしょう。さらに、ライフラインの停止や交通インフラの寸断によって、救援物資の到着が遅れ、復旧や救護活動がスムーズに進まない可能性があります。
●急性期の状況|災害による被害の把握
急性期は、災害発生から約1週間が経過し、現場が比較的落ち着きを取り戻す時期です。この段階では、被害状況の詳細な確認が進み、復旧に向けた計画が立てられます。避難所では生活が安定し始め、住民の一部が自宅に戻る動きも見られるでしょう。また、ボランティアや外部支援が本格的に加わり、復興に向けた初期活動が開始される時期でもあります。復興の基盤を築くための重要な期間といえます。
●亜急性期の状況|ライフライン・地域医療などの復旧
亜急性期は、ライフライン・地域医療などの復旧で日常生活が徐々に戻りつつある状況です。避難所の縮小や統合が検討されて夜間だけ避難所で過ごしたり、親戚の家に避難したり、と避難場所・避難者の行動に変化が目立つ時期です。
また地域医療では、介護が必要な方のために福祉避難所が設置されることも予想されます。
●慢性期の状況|復興ボランティアの撤退・復興支援が終了
亜急性期では、ライフラインや地域医療の復旧が進み、日常生活が徐々に戻りつつある状況です。この時期、避難所の縮小や統合が検討され、夜間だけ避難所で過ごす人や、親戚宅などに避難先を移す人が増えるなど、避難者の行動に変化が見られます。
また、地域医療では、特に介護が必要な方を支援するための福祉避難所が設置されることが予想されます。このように、避難所生活や地域全体の医療支援が次の段階へ進む移行期ともいえる重要なフェーズです。
●平穏期の状況|次の災害を想定した防災の準備期間
平穏期は、生活環境が安定し、医療や看護の支援がほとんど必要なくなる時期です。この期間は、次の災害に備えるための防災準備を進めるタイミングとなります。以下の取り組みを行い、災害時に備えましょう。
・防災グッズを備える:飲料水、非常食、懐中電灯などを準備する
・地域のネットワークを作る:災害時に連絡や救護活動がスムーズに行えるよう、自治体や避難所などとの連携を構築する
・災害訓練を実施する:学校や企業で避難訓練を行い、防災意識を高める
災害時には、まず自分の身を守ることが基本です。平穏期のうちに防災意識を高め、しっかり準備を整えて次の災害に備えましょう。
関連人気記事:ライフラインとは?意味・使い方や災害時に想定される被害と対策も解説
3.災害サイクルごとの医療や看護の役割

自然災害時は、時間の経過とともに医療や看護の役割が異なります。災害現場では、状況に応じた医療・看護活動が求められます。ここでは、災害サイクルの各フェーズごとの医療や看護の役割を解説しているので、内容を理解して自然災害時の救命救護活動に活用しましょう。
●超急性期の役割|早急かつ高度な医療ニーズで対応する
超急性期では、災害により外傷や熱傷などの負傷者が多く発生するため、迅速かつ高度な医療対応が必要です。この時期には、医療・看護活動以外にも以下の役割が求められます。
・救命救急を目的とした医療チームDMAT(Disaster Medical Assistance Team)の派遣要請
・避難所に避難している住民への医療・看護
・入院患者の域外医療機関への搬送など医療ができる場所の確保
・避難所に医療救護所の開設
さらに、災害発生前から治療を受けている患者には、電子カルテにバックアップされている地域住民の医療情報を活用し、災害後も継続的に適切な医療を提供しなければいけません。
●急性期の役割|巡回診療や医療・看護のサポートをする
急性期では、医療や看護の役割として、巡回診療や医療・看護のサポートが主な活動となります。この時期に必要とされる対応は以下の通りです。
・精神的ストレスや疲労による健康状態の確認
・災害による持病の悪化防止
・避難生活によるぜん息やエコノミークラス症候群の発症予防
急性期では、超急性期に比べて早急かつ高度な医療ニーズは減少しますが、医療チームや地域医療機関による巡回診療やサポートが引き続き必要です。
●亜急性期の役割|避難所生活者のケアをする
亜急性期は、避難所生活者を中心に、以下の医療・看護活動が求められる時期です。
・医療不足・衛生状況による病気の予防
・被災者または地域住民への巡回診療による心身の健康状態の確認
さらに、この時期には外部支援者による医療・看護活動のスタートが期待されます。
|
主な外部支援者・チーム |
|
JMAT(日本医師会災害医療チーム) |
|
DPAT(災害派遣精神医療チーム) |
|
JRAT(一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会) |
|
自治体の応援保健師・栄養士など |
この段階で、救命救急医療チームから地域医療チームへの支援体制が移行していきます。
●慢性期の役割|医療・看護支援活動を見極める
慢性期は、避難所や救護所が順次閉鎖され、医療チームの活動も終了に向かう時期です。この段階で必要な医療・看護活動には以下のものがあります。
・被災者の安定した日常生活や自立支援
・被災者の心のケア(抑うつ状態・PTSD・複雑性悲観・アルコール依存症などの治療)
・感染症や慢性疾患(高血圧・糖尿病や・高脂血症)などに対する看護
被災者が何を問題としているのかを常に把握し、必要な医療・看護を適切に提供しなければいけません。
●平穏期の役割|医療・看護分野の災害に対する準備をする
平穏期は復興活動が進み、日常生活が安定する時期です。この段階では次の災害に備えるため、以下のような医療・看護に関する防災活動が求められます。
|
活動・準備 |
活動内容 |
|
災害看護教育 |
災害看護セミナーなどの研修 |
|
防災訓練 |
避難訓練・応急救命訓練・救助訓練などの実施 |
|
医療機器・医薬品 |
人工呼吸器・吸引器関連、常備薬などの点検や準備 |
|
防災アイテム |
飲料水・非常食などの準備 |
|
防災教育プログラム |
災害に備えた防災・減災教育の作成 |
|
地域ネットワークの強化 |
防災活動を通して地域住民の関係性を構築 |
平穏期に適切な準備を進めることで、災害時にスムーズな医療・看護活動が行える体制を整えられます。
4.災害サイクルに備えた5つの取り組み

災害時でも、医療・看護活動が行えるように普段から災害に備えた取り組みが必要です。災害サイクルごとの状況に応じた、医療・看護の活動を行うために必要な取り組みを以下5つにまとめました。
・医療情報をバックアップする
・組織体制を明確にする
・防災教育を徹底する
・防災セット・訪問看護用備品を備える
・非常用電源を用意する
それぞれ詳しく解説しているので、災害時でもスムーズな医療・看護活動ができるように把握しておき、防災対策として取り組みましょう。
①医療情報をバックアップする
自然災害に備えて、地域の医療情報をバックアップしておく必要があります。災害時はインターネット環境が機能せず、必要な医療情報を入手できないこともあり得ます。そのため、電子カルテに保管している医療情報を、定期的にオフライン接続するサーバーやハードディスクにバックアップしておくことが重要です。インターネットがなくてもカルテの情報を見られるようにしておけば、災害時でも円滑に医療・看護が行えるでしょう。
②組織体制を明確にする
自然災害に備えて、医療・看護活動の組織体制を明確にする必要があります。災害時は、多発外傷や広範囲熱傷、挫滅症候群などの重篤救急患者の救命医療が予想されるためです。
負傷者や災害状況に応じて迅速で高度な医療・看護活動ができるように、組織内の役割分担を決めておきましょう。
③防災教育を徹底する
自然災害時でも、迅速な医療や看護活動が行えるように防災教育を徹底し、防災意識を高める取り組みが必要です。災害発生の仕組みや災害時の対処法・備えなどを防災教育で学び、災害状況に応じた適切な判断ができる知識の習得に努めましょう。
④防災セット・訪問看護用備品を備える
普段から防災セットや訪問看護用備品を備えておけば、災害時でも医療や看護活動が行えるでしょう。災害発生直後は、ライフラインの停止や交通インフラで必要な物資が届かないこともあり得ます。そのため、以下の防災セット・訪問看護用備品を備えておいてください。
|
一般的な防災セット |
訪問看護用備品 |
|
● 食料(一人当たり3日分) ● 飲料水 (一人あたり3リットル×3日分) ● 懐中電灯 ● 携帯ラジオ ● 非常用電源 ● 救急用品・衛生用品・生理用品 ● ヘルメット・ヘッドランプ・防災ずきん ● 軍手などの手袋 ● カセットコンロ |
● 衛生材料(滅菌手袋・消毒薬・ガーゼ・アルコール綿・蒸留水・注射器) ● 療養情報(人工呼吸器設定や身体的情報など) ● 飲み薬(1週間) ● 足踏み式・手動式の吸引器 ● 手動蘇生バッグ ● 予備吸引器 ● 吸引カテーテル ● 透明文字盤 ● 人工呼吸器回路1本 ● 人工鼻気管カニューレ1個 ● 外部バッテリー(非常用電源など) |
また災害時は停電も想定されるため、電力の確保も重要です。外部バッテリーとして非常用電源があれば、停電時でも一定期間医療機器へ電力供給が可能です。
⑤非常用電源を用意する
自然災害による停電で、医療機器が使えず医療・看護活動に支障をきたすこともあり得ます。そのため停電時でも医療機器が使えるように外部バッテリーとして、以下の非常用電源を備えてみてください。
・軽油発電機:燃料が軽油の大型発電機。常に一定のパワフルな出力で電力供給する。
・ガソリン発電機:燃料がガソリンの発電機。稼働音や振動が少ない。
・ガス発電機:燃料がカセットガスとLPガスの2種類ある発電機。カセットガスはガスボンベをセットするだけですぐに使える。
・ポータブル電源:コンパクトサイズで持ち運びがラクな可搬型蓄電池。ソーラーパネルと併用すれば燃料がなくても長期的な電力供給ができる。
なかでも、ポータブル電源はどこでもラクに持ち運びができる可搬型蓄電池で、屋内に限らず屋外での電力供給も可能です。停電時は、病院内や施設内どこでも持ち運んで電力確保ができます。
ポータブル電源は、電子レンジなどのキッチン家電・掃除機などの生活家電を動かせるから停電時は非常用電源として頼れる蓄電池です。リュックに入るコンパクトサイズのモデルや、大容量を備えたモデルなど幅広いラインナップが揃っています。停電時に必要な電力量や使い方に応じたモデルが選べるので、災害時の非常用電源として活用できるでしょう。
また、ソーラーパネルがセットになったポータブル電源も販売されています。停電が長引いても、ソーラーパネルで発電することで燃料がなくても電力の確保が可能です。自然災害時でも業務用のパソコンや医薬品冷蔵庫などへ電力供給ができるように、ポータブル電源を非常用電源として導入してみてください。
関連人気記事:停電時の病院を支える!非常用電源について詳しく解説
5.介護施設などのBCP対策にJackeryのポータブル電源がおすすめ!
自然災害による電力ストップで、災害現場では停電も想定されます。災害時でも電力を確保して、医療・看護活動ができるようにポータブル電源を備えてみてください。
なお、2024年4月から企業のBCP(※)が義務化され、これにより医療現場や介護施設などでは電力の確保も重要視されています。
※BCP(Business Continuity Plan):「事業継続計画」のことで、企業が自然災害・感染症・テロ攻撃などの影響でも優先して業務を行えるように、事前に対策や手段を取り決めておく計画。
関連人気記事:介護施設のBCP策定が2024年4月から義務化!やるべき対策まとめ
そこでBCP対策の一つに、停電時でも電力の確保ができる当社Jackery(ジャクリ)のポータブル電源がおすすめです。「一般社団法人防災安全協会」が定める「防災製品等推奨品認証」を取得しており、優れた耐震性・耐衝撃性能で震度7の揺れにも耐えられる設計です。災害現場でも業務用のスマートフォンでスタッフに連絡したり、タブレット端末で災害状況を確認したりしながら、安心して医療・看護活動が行えます。
またソーラーパネルがセットになった、「Jackery Solar Generator」もラインナップされています。ソーラーパネルで太陽光発電ができるので、長期間の停電でも電力復旧までの間、病院内や施設内の電力確保が可能です。
災害時でもスムーズな医療・看護活動ができるように、Jackery(ジャクリ)のポータブル電源を事業所や施設に1台導入しましょう。
もっと多くの商品を見る
6.災害サイクルでよくある質問
災害サイクルについて、以下3つの質問が多く寄せられています。
・災害サイクルの静穏期とはどういう意味ですか?
・災害サイクルの看護活動を教えてください。
・災害サイクルを図で表すことはできますか?
詳しく解説しているので、それぞれ見ていきましょう。
●災害サイクルの静穏期とはどういう意味ですか?
災害サイクルの静穏期とは、直接的な災害による影響がない期間のことです。また復興がある程度終了した時期にあたるので、災害に関する「防災訓練の実施」や「教育プログラムの作成」など防災・減災に取り組みます。
●災害サイクルの看護活動を教えてください。
看護活動は災害サイクルの期間ごとに異なるため、下記の表にした活動内容を参考にしてみてください。
|
期間 |
活動内容 |
|
超急性期(発災直後) |
自分と周りの安全確保 ライフラインの確認 トリアージ(治療・処置の優先順位)の決定 救命救護活動の初期対応 |
|
急性期(発災直後~72時間) |
救護所や避難所の開設 ライフラインの確保 救命・救急・集中治療看護 トリアージ(治療・処置の優先順位)の決定 遺体の処置や対応 こころのケア 巡回診療 救護物資の搬出や供給 復旧作業の推進 |
|
亜急性期(発生72時間~1カ月後) |
被災者の支援 保健や防疫、感染対策 疾患への看護 巡回診療 生活指導、こころのケア |
|
慢性期(発災数カ月~数年後) |
リハビリテーション看護 被災者の福祉・生活活動 自立支援 こころのケア 被災地の復興支援 |
|
平穏期(発災数年後) |
災害への備え 被災者の生活支援や精神的支援 被災地の復興支援 |
超急性期から平穏期までの経過を期間ごとに分けて、必要な医療・看護を行う活動を実施します。
●災害サイクルを図で表すことはできますか?
災害サイクルは、以下の図で表すことが可能です。

期間ごとに被災状況や医療・看護が変わるため、「今、被災者や被災地で必要な医療・看護のサポートは何か?」を考慮しながら活動を行います。
まとめ
災害サイクルのフェーズごとに応じたサポートを理解しておけば、災害時における医療・看護活動で何をすればよいか判断できます。
災害時は停電も想定され、病院内の電力が使えず医療・看護活動できないこともあり得ます。そのため、非常用電源としてポータブル電源を備えて、電力を確保することが不可欠です。
災害による停電時でも、病院内や施設内で安心して電力が使えるJackery(ジャクリ)のポータブル電源を1台備えておきましょう。