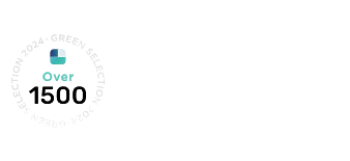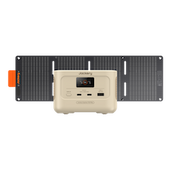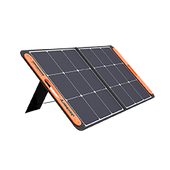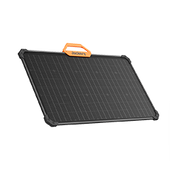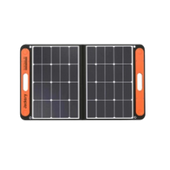1.防災対策に家庭でできること10選
防災対策のために家庭でできることは、大きく10の項目に分けられます。いずれも、日ごろからの準備が重要です。何をしておくとよいか、確認していきましょう。
その1:非常時に備えた情報収集
災害が発生した際は、短時間で判断し安全を確保しなければなりません。正しく判断するためには、日ごろから非常時に備えた情報収集を行っておくことが重要です。以下の項目は、ぜひ押さえておきましょう。
・避難所など、安全を確保できる場所
・避難所等への移動経路、および危険な箇所のチェック
・防災行政無線など、危険が迫っていることを知らせる情報の入手方法
安全な場所への移動は、夜間に行わざるを得ない場合もあります。大地震の直後や台風が迫る状況では、車を使った避難が危険となるかもしれません。徒歩での避難方法を確認するとともに、どのような危険があるか実際に歩いて確かめておくとよいでしょう。
またスマートフォンは便利ですが、電池がなくなると使えません。防災対策には電池がなくても情報を得られるラジオを備えることも、家庭でできることの一つです。手でハンドルを回して、またはソーラーパネルで充電するラジオが市販されています。
その2:自宅がある地域の危険度を知る
同じ災害に遭っても、被害の程度は地域により異なります。災害の内容や自宅がある場所の危険度により、被災時に自宅にとどまるか避難するかを適切に決める必要があるわけです。では、何を基準にして決めればよいのでしょうか。
自宅の危険度は、自治体が公表しているハザードマップで確認できます。洪水や土砂災害、地震などは代表的です。海が近い場所では、津波や高潮のハザードマップも用意されています。浸水の危険度や土砂災害警戒区域内かどうかなど、自宅のリスクを確認することも家庭でできる防災対策の一つに挙げられます。
もし自宅が危険な地域にある場合は、避難のタイミングが重要です。台風や川の氾濫、津波などの災害が迫る前に、また大きな地震に遭った場合は速やかに、安全な場所へ避難しましょう。
その3:家具やガラスの安全性を確保する
家具やガラスなど住まいの安全性を確保することは、家庭の防災対策において重要です。家庭でできる防災対策としてよく取り上げられている方法を、以下の表に示しました。
|
家具や設備の種類 |
対応方法 |
有効な災害の例 |
|
重い、または高さのある家具 |
突っ張り棒や粘着マットを設置するなど、転倒防止対策を施す |
地震 |
|
重いもの |
なるべく家具の上に置かない |
地震 |
|
重要な、または水濡れを避けたいもの |
2階など、なるべく高い位置に置く |
水害 |
|
ガラス |
飛散防止フィルムを貼り、鋭利な破片をできにくくしてけがのリスクを下げる |
地震、風水害 |
いずれも被災時の被害を抑えられる方法です。災害は、いつ起こるかわかりません。早めに対策を施し、より安全な住まいにしましょう。
その4:非常食や家庭用品を備蓄し、保存状態を定期的にチェックする
物流が滞りライフラインも寸断されるほどの大きな災害に遭った場合は、店舗での購入や飲食店の利用が難しくなります。被災した場合は、しばらく自宅にあるもので過ごさなければなりません。大規模災害に備えて、1週間分の食料や飲料水、家庭用品や非常用トイレなどを備蓄しておきましょう。
店舗ではよく「非常食」や「防災セット」を見かけますが、家庭の防災対策に必須のものではありません。例えば食品なら、缶詰やレトルトパックなど長持ちする食品の購入で家庭の防災対策になります。定期的に購入して古いものを食べていく「ローリングストック」を行うと、賞味期限切れの心配がなくなるためおすすめです。
防災対策として備蓄しておくべき具体的なものは、以下の記事をご参照ください。
関連人気記事:防災グッズで本当に必要なものって知ってる?備蓄用と持ち出し用に分けて徹底解説
その5:停電に備える
被災時に停電となるケースは、意外と多いものです。地震や津波、土砂災害、暴風や水害、豪雪は、いずれも停電の原因となり得ます。2019年の台風15号では、電気が20日間近く途絶えた家庭もありました。電気が使えない事態に備えて、ソーラーパネルとポータブル電源の準備をおすすめします。
事前に商用電源(AC100V)を使えない生活を体験しておくと、停電にもスムーズに対処できるでしょう。「おうちキャンプ」は、停電に備えて家庭でできることとしても有効です。
関連人気記事:非常用ポータブル電源おすすめ9選!選び方や災害での使い道も解説
その6:災害の「備えリスト」をチェックして持ち出し袋を用意する
被災した後に自宅で過ごせればよいですが、自宅の危険度や被災状況によっては安全な場所への避難が必要な場合もあります。迅速に避難できるよう、持ち出す物を事前に用意し非常用持ち出しバッグに入れておくことも、家庭でできることとして重要です。非常用持ち出しバッグに入れておきたい物の一例を、以下に挙げました。
|
基本の備えリスト |
● 水 ● 食料 ● 防災ヘルメット ● 防災ずきん ● レインコート ● 軍手 ● 懐中電灯 ● 携帯ラジオ ● 携帯充電器 ● 予備の電池 ● マッチ ● ろうそく ● ペン・ノート |
● 消毒用アルコール ● 救急用品 ● 使い捨てカイロ ● ブランケット ● タオル ● 洗面用具 ● 歯ブラシ・歯磨き粉 ● ウェットティッシュ ● 携帯用トイレ ● 体温計 ● 常備薬 ● マスク ● 貴重品 |
|
子どもの備えリスト |
● ミルク ● 使い捨て哺乳瓶 ● 離乳食 ● 携帯カトラリー ● 紙おむつ ● おしりふき ● 抱っこ紐 ● 子どもの靴 |
|
|
女性の備えリスト |
● 生理用品 ● おりものシート ● サニタリーショーツ ● 中身の見えないゴミ袋 ● 防犯ブザー・ホイッスル |
|
|
高齢者の備えリスト |
● 紙パンツ ● 補聴器 ● 杖 ● 介護職 ● 入れ歯・洗浄剤 ● 吸水パッド ● 常備薬 ● お薬手帳のコピー |
|
参考:首相官邸ホームページ
なかでも「水」と「食料」は多めに備えておきたい備蓄品です。東日本大震災のとき、宮城県の約8割の避難所でタンパク質やビタミンを補給できる食品が不足していました。栄養不足は健康面や免疫面に悪影響を及ぼす可能性があります。穀物類のほかにサバ缶・野菜ジュースなども1週間×家族分備えておきましょう。
参考:国際災害栄養研究室
その7:家族どうしの連絡方法を決めておく
被災地では以下の理由により電話がつながりにくく、通信も行いにくいケースも少なくありません。
l 通話したい方や通信量が大幅に増加する(通常時の数十倍に増加する場合もある)
l 基地局や電話回線の故障が発生する
いつも活用している携帯電話やSMS、LINEでは、なかなか連絡が取れないかもしれません。公衆電話からの発信は優先的につながるものの、街中に設置されている公衆電話の台数が大きく減っているため、待ち時間が長くなりがちです。
被災した際に備えて家族の連絡方法を決めておくことも、家庭の防災対策の一つです。代表的な方法を、以下に挙げました。
・遠くの親戚に連絡役を担ってもらう
・災害用伝言ダイヤル「171」を活用する
・災害用伝言版を利用する
災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板は、体験利用できる日も用意されています。事前に使い勝手を試しておくことも、家庭でできることの一つです。
関連人気記事:災害時の連絡手段5選を徹底解説!携帯以外の安否確認方法も紹介
その8:近所付き合いをしておく
日頃からの近所付き合いも、家庭の有効な防災対策に挙げられます。話しやすい関係を作っておけば被災時に助け合うことができ、災害が迫ったときにも避難を呼びかけやすいでしょう。声をかけてもらうことで難を逃れる確率も高まります。
1995年の阪神淡路大震災では要救出者が35,000名も発生しましたが、そのうち27,000名もの方が家族や近隣の方々により救出されました。近所付き合いは家そのものの防災対策を高める方法ではありませんが、いざというときに助かる確率を上げる方法として有効です。
その9:生命保険や損害保険の契約内容を確認する
災害に遭った際には、けがを負ったり死亡したりする可能性もあります。また家屋や家財が損傷するおそれもあります。生命保険や損害保険の契約内容を確認することも、防災対策として重要です。被害に遭った場合の手続き方法や必要な書類も確認しておくと、スムーズに申請できます。
生命保険の場合は、保険金や保障内容が適切かどうか確認してください。もし不足する場合は、保障額を増やす必要があります。契約を見直す、新しい保険に入るなどの方法で対応しましょう。
一方で損害保険では加入している保険の数や金額に関わらず、被害に遭った金額しか支払われません。保険でカバーされていない家屋や家財がある場合は、補償内容をアップする必要があるでしょう。しかし今の保険でカバーできている場合は、今よりも多くの保険を契約することに意味はありません。
なお地震への防災対策は、地震保険に加入する必要があることに注意してください。
その10:ペットに対する備えも忘れずに
ペットを飼っている家庭は、ペットに関する防災対策も必要です。避難は飼い主と同行する「同行避難」が基本です。他の避難者に不快な思いをさせないよう、日ごろからしつけをしっかり行っておきましょう。ペットフードやペット用品の備蓄、キャリーバッグの準備なども、家庭でできることの一つです。
またペットは、飼い主とはぐれる可能性もあります。その場合に備えて、首輪や迷子札、マイクロチップなどをつけておきましょう。迷子になっても、飼い主のもとに戻る確率が高まります。
2.防災対策は徹底的に!家の中の安全対策チェックリスト
家の中の安全対策は、次のチェックリストをもとに家族全員で取り組みましょう。
●家の中で安全な場所を確認する
●消火器具の場所を確認する
●火気器具の安全点検をする
●持ち出し袋の点検・置き場所を確認する
「地震が起きたら、家の中のここに避難する!」という場所を決めておけば、地震で大きく揺れたときも冷静に避難できます。
火災が起きても落ち着いて対処できるように、消火器具の場所の確認や火気器具の安全点検をすることも大切です。
持ち出し袋に入れている食料や水の消費期限が過ぎていないかも定期的にチェックし、家族全員で起き場所を確認しましょう。
参考:東京都防災ページ
3.家庭に必要な防災対策・地震備えグッズ5選

大地震が起きたら必ず避難所へ避難するわけではなく、自宅で過ごす「在宅避難」になる場合もあります。ここで紹介する家庭の防災対策・地震備えグッズを参考にしながら、自宅で安心して過ごせるように準備しましょう。
①家族分の毛布・寝袋
在宅避難では、窓ガラスが割れて散乱したり、大きな家具が倒れたりしてベッドや布団が使えない場合があります。そのような状況に備えて、家族分の毛布と寝袋を用意しましょう。
とくに冬場は、死亡リスクがある「低体温症」に配慮しなければいけません。能登半島地震では、亡くなった238人のうち32人が、低体温症・凍死などの「寒さ」が原因で命を落としました(※2024年1月時点)。
なかには自宅で低体温症になり亡くなっていた方もいるため、在宅避難でも暖がとれるように、家族分の毛布・寝袋を必ず備えてください。
参考:NHK
関連人気記事:防災用寝袋は必要か?寝心地に関わるマット・寝袋の選び方や防災グッズも紹介
②置いて使える懐中電灯・ランタン
大地震が発生すると、多くの地域で停電が起こります。夜になると家の中は真っ暗になるでしょう。そのような状況でも次のメリットを得られるように、家庭防災で置いて使える懐中電灯・ランタンを備えておくことが大切です。
● 真っ暗な家の中を安全に移動できる
● 散乱物を踏んで怪我をするリスクが減る
● 「明かりがある」と安心感を得られる
真っ暗な環境でも安心・安全に過ごせるように、明かりは必ず確保してください。手持ちの懐中電灯は置いて使いにくいため、必ず「置いて使える懐中電灯・ランタン」を選ぶのがポイントです。
関連記事:防災ライトおすすめ10選|必要性・選び方も詳しく解説
③多めの簡易トイレ
地震により断水すると、いつも使っている水洗トイレが使えなくなります。トイレができない・我慢しなければいけない状況をつくらないために、簡易トイレは多めに用意しておきましょう。
目安としては、1人あたり35回分(7日分)の簡易トイレが必要です。成人の1日の平均排泄は1人あたり5回といわれており、経済産業省でも1週間分のトイレ備蓄を推奨しています。
参考:内閣府防災情報のページ
④大きめ容量のポータブル電源と折り畳みソーラーパネル

あらかじめ電気を溜めておける「ポータブル電源」は、家庭の防災対策として1家に1台は備えておきたい必需品です。折り畳みソーラーパネルとのセット使いで、停電時に次のように役立ちます。
● 電気を自給自足できる
● 夜間でも給電できる
● 避難先に持っていける
ポータブル電源×ソーラーパネルなら、長引く在宅避難時にも繰り返し電気を自給自足できます。軽量かつ稼働音が静かな製品が多く、避難先に持っていきやすいのもポータブル電源×折り畳みソーラーパネルの魅力です。
たとえば「Jackery ポータブル電源 3000 Newセット」にはハンドルが付いており、キャリーケースもセットされているので、持ち運びやすいです。稼働音も30デシベル以下の”ささやき声”レベルなので、夜間でもまわりに迷惑をかけずに使用できるでしょう。
関連人気記事:【個人向け】ポータブル電源は災害時にいらない?不要派の意見や役立つ4つのシーンを解説
⑤断水しても使える衛生用品
地震などの災害で断水しても使える衛生用品には、次のようなものがあります。
● ドライシャンプー
● 歯磨きシート
● 携帯トイレ
● ウェットティッシュ
● 手指消毒アルコール
自宅に水がきていなくても、ドライシャンプーがあれば簡易的に頭を洗えます。備蓄水をなるべく飲み水として使えるように、歯磨きシートや携帯トイレで節水することも大切です。
食事の前にウェットティッシュやアルコール消毒で手指の衛生管理をすれば、感染症対策にもなるでしょう。
関連人気記事:停電中でもトイレは使える?タンクレスの流し方・断水時の注意点や対策を解説
4.家庭の防災対策におすすめ非常用電源3選
●Jackery Solar Generator 2000New ポータブル電源ソーラーパネルセット|3~4人の家庭防災におすすめ
●Jackery Solar Generator 1000 New 100Wポータブル電源ソーラーパネル|2~3人の家庭防災におすすめ
●Jackery ポータブル電源 3000 New セット|4人以上の家庭防災におすすめ
5.家庭でできる防災対策についてよくある質問
最後に、家庭でできる防災対策についてよくある質問を紹介します。
①地震に備えて今、やるべきことは?
地震に備えて今やるべきことは、次の7つが挙げられます。
● 避難経路を確保・確認する
● 自宅周辺の防災マップを確認する
● 家具やガラスの安全性を確保をする
● 非常食や備蓄品を備える
● 持ち出し袋を準備する
● 非常用のポータブル電源を備える
● 家族の安否確認方法を話し合う
今からでもできることはたくさんあるので「あのとき対策しておけばよかった……」と後悔しないよう、できるだけ早めに取り組みましょう。
②日本はどのような災害対策の取り組みをしているの?
国土交通省では、30年以内に発生するといわれる「首都直下地震」において次のような災害対策に取り組んでいます。
● 帰宅困難者や負傷者を収容する施設の整備・機能強化
● エレベーターにP波感知型地震時管制運転装置を積極的に設置
● ハザードマップを作成・公表し液状化に対する防災意識を向上
このほかにも、日本ではさまざまな災害対策に取り組んでいます。国土交通省のホームページに災害種・地方区分別で詳しく載っているので、気になる方はチェックしてみてください。
参考:国土交通省
③地震の備えで大切なことは?
地震の備えで大切なのは、自分の命を自分で守る「自助」の意識をもつことです。1人ひとりが自分の身の安全を守ることで、災害時の生存確率が高まります。
自助に取り組むためには、家の中の家具や家電を固定したり、自宅周辺の防災マップを確認したりなどの備えが必要です。記事冒頭で紹介した「防災・地震対策に家庭でできること10選」を参考にしながら、確実に防災対策を進めていきましょう。
④災害時になくて困ったものは?
災害時になくて困ったものは、主に次のようなものが挙げられます。
● 水
● 食料
● 簡易トイレ
● 防寒具
● 救急セット
● スマホの充電
生きるうえで欠かせない食料・水・簡易トイレは、少なくとも1週間×家族分は備えておきましょう。冬場は「防寒具がなくて、寒くて眠れなかった」と振り返る被災者が多いため、毛布やアルミシートなどの防寒対策も必要です。
「311のとき、停電してるのにその日に限って雪すごい降ってて本当に眠れないくらいめっっちゃ寒かったのよ(寝たけど)
たから今日もし停電しても寒くないように家の中暑くしておく」
引用:X
また、停電が長引くと電力が足りず、スマホの充電ができなくなります。地震情報をチェックできないのは災害時に致命的です。災害時に適切に行動できるように、ポータブル電源とソーラーパネルの両方を備えていつでも最新情報を拾えるようにしましょう。
ポータブル電源とソーラーパネルの活用で防災対策を万全に
防災対策として、家庭でできることは数多くあります。「被害に遭わないこと」「安全に避難できること」はもちろん重要ですが、「被災後の生活をできるだけ快適に過ごす」ことも重要なポイントです。ポータブル電源とソーラーパネルは万全な防災対策を取り被災後の暮らしを快適にするうえで、欠かせないアイテムです。
Jackeryの製品は、一般社団法人防災安全協会が認定する「防災製品等推奨品」を取得しています。多くのユーザーが活用しているJackeryのポータブル電源とソーラーパネルを、防災対策にぜひ加えてみてください。