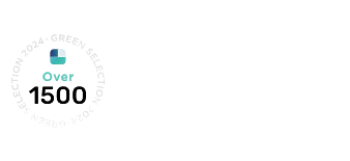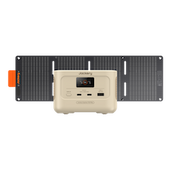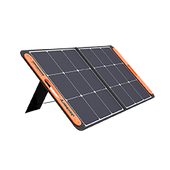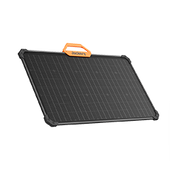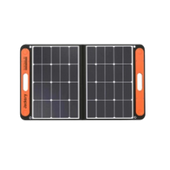1.【防災豆知識12選】意外と知らない災害対策
意外と知らない災害対策として、防災豆知識12選を解説します。
・食器の洗い物を減らす方法
・床の冷たさを和らげる方法
・簡易トイレ以外で用を足す方法
・明かりの代わりを用意する方法
・マスクの代わりを用意する方法
・家具の転倒リスクを減らす方法
・子どもを探しやすくする方法
・非常食の消費期限を切らさない方法
・スマホ以外で安否を確認する方法
・災害の停電時に使える炊飯方法
・災害の停電時に体温管理をする方法
・毎日の生活で使っているものが少しの工夫で防災アイテムになる
一つずつ確実に押さえていきましょう。
①食器の洗い物を減らす方法
災害時には断水の可能性があるため、食器の洗い物を減らす方法が大切です。具体的には次の方法が役立ちます。
・食器をラップで覆う
・新聞紙製の食器をビニールで覆う
・キッチンバサミで食材を切る
キッチンバサミがあればまな板を使わずに済む分、節水可能です。歯磨きやうがい、手洗いなど、衛生面で欠かせない水を確保するためにも、食器類の洗い物は減らしましょう。
②床の冷たさを和らげる方法
床の冷たさを和らげる方法として、ダンボールやエマージェンシーシートがおすすめです。この2つには体温を維持する効果があり、床が冷たい避難所で就寝しても体温低下を抑えられます。
実際に、熊本地震からダンボールベッドを使う避難所が増え、2020年7月に豪雨が集中した九州でもほぼすべての避難所に支給されました。
とはいえ、ダンボールだけでは防寒対策として不十分です。災害支援用の防寒具の数にも限りがあるため、毛布やUSB式湯たんぽなどを自前で用意し、停電時の自宅や避難所での寒さに備えましょう。
参考:日本赤十字北海道看護大学「寒冷期の避難生活を想定した就寝資材の検討」
関連人気記事:フローリングの寒さ対策を徹底解剖!100均グッズや賃貸OKのDIYも紹介
③簡易トイレ以外で用を足す方法
簡易トイレが用意できない場合、地域ごとの備品倉庫にあるマンホールトイレが役立ちます。
マンホールトイレは、マンホール上に仮設トイレを設置して用を足せる仕組みです。防災訓練に参加すれば、設置場所や組み立て方法を学ぶことができます。
実際に、熊本地震や東日本大震災においてマンホールトイレが活躍しました。トイレを使えなければ、食事や水分摂取を我慢して栄養失調にもなりかねません。各市役所のホームページで、マンホールトイレの詳細を確認しておきましょう。
関連人気記事:停電中でもトイレは使える?タンクレスの流し方や断水時の注意点や対策を解説
④明かりの代わりを用意する方法
災害時に停電する場合に備えて、明かりの代わりを用意しておいてください。例えばサラダ油があれば、次の方法で電気を使わずに室内を明るくできます。
・耐熱ガラスのコップを用意する
・キッチンペーパーをひも状にする
・キッチンペーパーの中央をアルミホイルで巻く
・キッチンペーパーが垂直になるようにコップ中央に固定する
・サラダ油をコップに入れる
・キッチンペーパーに油が染みたら火をつける
油を足せば何時間でも使えますが、コップが倒れると火事につながります。周りから引火しやすい物を除けておき、コップは両面テープなどで固定しておきましょう。
参考:東京都 Tokyo Metropolitan Government「サラダ油で簡易ランプ」
関連人気記事:【停電対策!】明かりの代わりになるもの7選|ペットボトルで手作りも可能
⑤マスクの代わりを用意する方法
大判のハンカチはマスクの代替品としておすすめです。建物の倒壊で発生した土埃や火災の噴煙など、災害時には喉と鼻にダメージを与える要因が多数あります。災害時のスムーズな避難には、喉と鼻を守るグッズが欠かせません。
コロナが蔓延した結果、マスクが買い占められたケースを知っている人は多いでしょう。ハンカチなら買い占めの心配もなく、簡単に購入できます。
火災に巻き込まれたときの死因第2位は、噴煙による一酸化炭素中毒です。火災から安全に避難するためにも、マスクや大判のハンカチを用意しておきましょう。
参考:内閣府政策統括官(防災担当)「できることから始めよう!防災対策 第1回‐内閣府防災情報のページ」
⑥家具の転倒リスクを減らす方法
家具の転倒リスクを減らす方法として、以下の方法が効果的です。
|
家具類 |
固定方法 |
|
タンス |
● 床側をストッパーで固定する ● 天井部分をポール式器具で押さえつけて固定する |
|
食器棚 |
● L字型金具やワイヤーで壁に固定する ● 開き戸を留め具で固定する |
|
本棚 |
● 重い本を下段に集中させる ● 本が飛び出さないようにベルトを取り付ける |
|
テレビ |
● 粘着マットで固定する ● ワイヤーで壁や台に固定する |
|
冷蔵庫 |
● 背面をワイヤーで壁に固定する |
他にも、食器棚や窓にガラス飛散防止フィルムを貼れば怪我のリスクを軽減し、迅速に避難できるでしょう。
地震が起きた際、家具の転倒に巻き込まれる被害が多発します。家具の固定を徹底して地震に備えましょう。
参考:政府広報オンライン「災害時に命を守る一人ひとりの防災対策」
関連人気記事:地震の備えとして家具にできる7つの対策|防災グッズと二段構えで万全
⑦子どもを探しやすくする方法
緊急時に子どもを探しやすくするために、写真を撮っておきましょう。写真があれば第三者に人相をはっきり伝えられるため、誰かに人探しを頼むことが可能です。
また、子どもだけでなく親の写真も子どもに持たせれば、お互いに見つけやすくなります。災害時に少しでも早く再会できるように、互いの写真を持っておくのがおすすめです。
⑧非常食の消費期限を切らさない方法
非常食は基本的に長持ちしますが、消費期限がないわけではありません。緊急時でも安全に食べられるように、ローリングストック法を実践しましょう。
ローリングストック法は、普段から非常食を消費し、足りなくなった分を補充することで食材の質を保つ手法です。また、普段から食べておけば、苦手な食べ物やアレルギーを調べることもできます。
日頃の食事に比べて味も変わるため、非常時の食生活に慣れるためにも、ローリングストック法はおすすめです。
関連人気記事:災害時に非常食になるもの10選!いざという時に備えて安く買い揃えよう
⑨スマホ以外で安否を確認する方法
災害時には電話回線がパンクし、スマホでの連絡は難しくなるため、確実に連絡を取れる方法が欠かせません。
スマホ以外で安否を確認する方法として、公衆電話が有効です。公衆電話は通信規制がかからないため、回線混雑時にも電話機能を使えます。NTTから独自の電力供給も受けており、停電発生時にも使用可能です。
ただし、機種によっては硬貨やテレホンカードが必要です。スマホに慣れた年代は使い方がわからない人もいると思われるため、家族間で使い方を共有しておきましょう。
関連人気記事:災害時の連絡手段5選を徹底解説!携帯以外の安否確認方法も紹介
⑩災害の停電時に使える炊飯方法
停電時には家電が使えなくなりますが、カセットコンロと鍋などがあれば、災害時でも炊飯できます。道具の種類ごとに必要な加熱時間は以下のとおりです。
|
道具の種類 |
基本的な加熱時間 |
注意点 |
|
土鍋 |
沸騰したら火を止めて20分蒸らす |
鍋が焦げないように、こまめに様子を見る |
|
圧力鍋 |
15~20分ほど火にかける |
圧力鍋ごとに加熱時間は変わるため、説明書の加熱時間を守る |
|
フライパン |
沸騰から15分経過後、火を止めて5分蒸らす |
炊きムラができないように、弱火で均等に混ぜる |
お米には炭水化物を始めとした、さまざまな栄養素が詰まっています。災害時に栄養を確保するためにも、鍋類を使った炊飯方法を押さえておきましょう。
⑪災害の停電時に体温管理をする方法
健康的な体調管理には、防寒・熱中症対策の充実が必須です。災害の停電時でも体調を管理できる方法として、次の例があげられます。
|
防寒対策 |
● USB式湯たんぽ ● 使い捨てカイロ ● 薄い服の重ね着 ● 保湿性に優れた下着 |
|
熱中症対策 |
● こまめに水分摂取する ● 衣服を緩めて涼しい場所で寝かせる ● 首回り・脇の下・太ももの付け根を冷やす |
他にも、持ち運べるバッテリー装置「ポータブル電源」がおすすめです。ポータブル電源はAC電源(コンセント)が使えるため、停電時でも家電を動かせます。
USB式の湯たんぽやコンセントにしか接続できない扇風機など、さまざまな家電を使って寒さと暑さの両方に対処可能です。衣類や飲食物以外の体温管理方法を充実させたい人は、ポータブル電源を用意しましょう。
参考:消防庁「大規模停電下における熱中症の予防対策について」
⑫毎日の生活で使っているものが少しの工夫で防災アイテムになる
日用品を少し工夫するだけで、防災アイテムに早変わりします。実際の活用方法を以下にまとめました。
|
道具 |
活用方法 |
|
新聞紙 |
毛布の間に挟んで断熱効果を高める |
|
ラップ |
包帯を固定する道具として使う |
|
ジップロック |
スマホや貴重品が濡れないように入れておく |
|
ビニール袋 |
清潔な布と組み合わせてオムツを作る |
|
衣類 |
袖を棒に通して担架を作る |
このように、日用品は防災対策に活かせる可能性を秘めています。災害用の防災アイテムが不足する場合に備えて、日用品の活用方法を覚えておきましょう。
2.【ケース別】防災に役立つ!災害時のサバイバル術と豆知識ガイド

災害時に役立つサバイバル術と豆知識を、ケース別にまとめました。
・地震発生時のサバイバル術と豆知識
・津波発生時のサバイバル術と豆知識
・台風発生時のサバイバル術と豆知識
それぞれ詳しく解説します。
●地震発生時のサバイバル術
地震発生時に役立つサバイバル術は、場所や状況によって変わります。それぞれのケースで必要な防災対策は、次のとおりです。
|
場所 |
重要な行動 |
|
屋内 |
● 家具から離れて机の下に隠れる ● 地震が収まってから火元を消す ● 避難経路を確保する |
|
大型施設 |
● 従業員の指示を待つ ● 照明や設備から離れる ● 出入口や階段で走らず移動する |
|
屋外 |
● 山や崖、急斜面から離れる ● 塀や自動販売機から離れる ● 公共機関ではつり革や手すりをつかんで体を固定する ● 自動車は鍵を着けたまま左側に停める |
他にも、学校やコンビニなどの施設は、緊急時にさまざまな支援を行ってくれます。トイレの貸出、飲料水や休憩所の提供、道路情報の告知など、地震で帰宅困難な人へのサポートが豊富です。
地震は自然災害のなかでも、いつどこで起きるかわかりません。地震発生時に危険な行動を取らないためにも、サバイバル術を身に付けましょう。
参考:内閣官房内閣広報室「地震では、どのような災害が起こるのか」
関連人気記事:地震が起きたらどうすればいい?地震発生時の対応と備えておきたいものも紹介
●津波発生時のサバイバル術
内閣府の防災情報によれば、地震が起きてから2分で津波が押し寄せてくるケースもあります。地震の強さに関係なく、津波警報が発令された場合はすぐに高台に避難しなければなりません。
付近に高台がなければ「津波避難場所」や「津波避難ビル」の標識が貼られている建物への避難がおすすめです。「津波避難場所 〇〇市」と検索すれば避難所を発見できるため、土地に慣れていない旅行者や出張中の営業社員でも、避難先をリサーチできます。
なお、チリでは地震発生から20時間以上かけて津波が到達した事例もありました。地震が起きていなくとも津波が襲ってくる事態もあるため、津波警報を聞き逃さないようにしましょう。
参考:内閣官房内閣広報室「津波では、どのような災害が起こるのか」
関連人気記事:高潮と津波の違いを徹底解説!過去の被害例や備えるべき防災グッズを伝授
●台風発生時のサバイバル術
旅行や出張中に台風が発生したときには、防災グッズが不足している可能性があるでしょう。しかし、国土交通省が推奨しているハザードマップを活用すれば、危険区域や避難経路を簡単にチェックできます。
現在地の住所を入力するだけで、洪水・道路情報・土砂災害などの情報をリアルタイムで把握できるため、初めての土地でも安全な避難が可能です。台風以外の災害時にも役立つので、防災対策を充実させたい人はハザードマップの使い方を確認しておきましょう。
参考:国土交通省 水管理・国土保全局 防災課「ハザードマップポータルサイト」
関連人気記事:台風の被害とは?日本で起きた事例や台風対策に必要な防災グッズを紹介
3.災害支援開始までは約3日!非常時に必須のポータブル電源とソーラーパネルセット

災害発生時は人命救助が優先されるため、食料の支給やライフラインの復旧が行われるまでの約3日間は、自分で生き残らなければなりません。
そんな非常時に役立つのが、ポータブル電源とソーラーパネルのセットです。
ポータブル電源は、大容量・高出力・優れた携帯性の3拍子が揃った防災グッズ。例えば、Jackery(ジャクリ)のAC出力(コンセント)付き最小モデルと大容量のモバイルバッテリーを比べると、スマホの充電回数で約2倍の差があります。
・Jackery ポータブル電源 240 New:約11回
・20,000mAhのモバイルバッテリー:4~5回
上記の「240 New」はティッシュボックス2つ分ほどのサイズと大きめですが、合計5つのポートを備え、災害時に多人数のスマホを充電できます。ソーラーパネルもあればコンセントなしで充電できるため、災害支援開始までの時間が延びた場合にも対処可能です。
他にも、電子レンジやエアコンなど、電力消費が激しい家電を動かせる製品も揃っています。
なおJackery(ジャクリ)には、巨大地震に襲われた能登半島や大雨の被害を受けた山形県に、ポータブル電源を無償提供した実績があります。確かな実績を持つ製品を探している人には、Jackery(ジャクリ)がおすすめです。
もっと多くの商品を見る
4.防災豆知識についてよくある質問
防災豆知識についてよくある質問にお答えします。
・防災対策で1番重要なことは?
・簡単にできる防災対策の豆知識は?
・防災知識を身に付ける簡単な方法は?
万全の防災対策で災害に備えましょう。
●防災対策で1番重要なことは?
防災対策で1番重要なのは、まず自分の安全を最優先にすることです。災害時に衣食住が整わない状態で周りを優先すれば、体調悪化を招いて逆に迷惑をかけるかもしれません。
自分の安全を確保してから周りと助け合い、国や自治体の支援を待つのが災害の被害を抑える最適な方法です。
●簡単にできる防災対策の豆知識は?
簡単にできる防災対策として、次の3つがあげられます。
1.居住地ごとに特化した防災アプリのインストール
2.非常食を日頃の食生活に活かすローリングストック法の実践
3.現在地の危険性をすぐに把握できるハザードマップの活用
上記の防災対策は日常生活に取り入れやすく、防災対策を習慣化できるでしょう。防災アプリやハザードマップは、土地の成り立ちや過去の被害を参照できるため、危険な地域への理解がより深まります。
防災対策をどう始めたらいいかわからない人は、日常的に実践しやすい防災対策から身に付けるのがおすすめです。
●防災知識を身に付ける簡単な方法は?
防災知識を身に付ける簡単な方法としては、クイズ形式がおすすめです。小さな子どもが学べる内容から大人でも難しいクイズまで、幅広い防災知識を学べます。
なお、防災クイズについて下記の記事でも詳しく解説しています。災害対策の内容も充実しているので、防災知識をより深めたい人におすすめです。
関連人気記事:【防災クイズ】小学生から大人・高齢者向けまで!防災対策に役立つ豆知識
まとめ
この記事では、意外と知らない防災豆知識と、災害別のサバイバル術を解説しました。自然災害から身を守るためには、防災対策を日常に取り入れることが重要です。
未知の知識を一気に覚えようとしても身につかず、防災対策を諦めてしまう人もいるでしょう。非常食の日常化や防災アプリのインストール、ハザードマップなどの確認が防災対策を充実させる第一歩です。
災害支援が始まるまで3日ほどかかるため、助けが来るまでは自力で生き延びるための対策が不可欠。この記事で紹介した豆知識やポータブル電源を活用し、自分と大切な人が生き残る確率を高めましょう。