1.電池が液漏れする原因
電池には「電解液」と呼ばれる溶液が含まれています。液漏れとは、この電解液が何らかの原因で外部に漏れ出した状態のことを指します。
まずは以下の状況において、液漏れする原因を見ていきましょう。
・使用中・使用後の液漏れ
・未使用での液漏れ
順番に解説していきます。
①使用中・使用後の液漏れ
電池の使用中や使用後の液漏れは「過放電」が原因です。
過放電とは、電池が通常の使用限界を超えて電気を供給し続けようとする状態のことです。機器で電池を完全に使い切ったり、長期間放置したりする場合に起こります。この時、電池内部で発生している化学反応が過剰に進み、ガスが発生。電池内の圧力が高まり、密閉されていた部分が破損することで液漏れが起こります。
液漏れを防ぐためには、電池を完全に使い切る前に交換し、長期間使用しない場合は取り外すことが大切です。液漏れを未然に防ぐために、過放電の原因となる状況を避けるよう心がけましょう。
②未使用での液漏れ
未使用の電池で液漏れする原因は以下の3つです。
1.衝撃が加えられ変形
2.保存環境が悪い
3.使用期間を超えた保管
電池が衝撃を受けて外装が損傷すると、内部の電解液が漏れ出すことがあります。重い物や硬い物との衝突や、高い位置から落下などで損傷する場合があるため、取り扱いには十分注意しましょう。
他にも劣悪な環境下での保管や、使用期間を超えた保管も液漏れの原因の一つです。電池は高温や湿気に弱いため、保管状況が悪いと内部の化学反応が進み、液漏れのリスクが高まります。また、保管状況が良くても使用期間を超えると、電極や電解液が劣化し液漏れする可能性もあります。未使用の電池であっても、取り扱いや保管には十分注意しましょう。
2.液漏れした電池や機器の捨て方・掃除方法

液漏れした電池を扱う際は、必ずゴム手袋を着用し、直接触れないように注意してください。ゴム手袋を装着したら電池を取り外し、乾いた布やティッシュで拭き取ります。端子部分をテープで絶縁した後、ビニール袋に入れて密封してください。その後自治体の指示に従って適切に廃棄します。
機器内部に漏れた電解液も電池と同様に、乾いた布やティッシュで拭き取りましょう。きれいに拭き取れて機器に損傷がなければ、再び使えます。消毒液で拭き取り、完全に乾かしてから新しい電池を入れてください。
電池の液漏れがひどく、損傷や故障が見られる場合は、修理または処分を検討しましょう。処分する際は、自治体のルールに従って適切に行うことが大切です。安全に処理するためにも、上記の内容をしっかり守って対応してください。
関連人気記事:電池の捨て方はコレ!種類別の処分方法と電池のゴミを減らす4つの方法
3.電池の液漏れが付いたときの対処法3選
液漏れした電池を処理している際に、誤って身体や衣服に付いてしまうこともあるかもしれません。電池から漏れた液が付いてしまった場合は、以下の方法で対処しましょう。
・手や体に付いた場合|すぐに水で洗い流す
・衣服に付いた場合|水ですすぐ
・家具や床についた場合|濡れた布で拭き取る
詳しく解説していきます。
①手や体に付いた場合|すぐに水で洗い流す
液漏れした電解液が手や体に付いた場合は、速やかに水で洗い流してください。放置すると皮膚が炎症を起こす可能性があるため、早めの処置が大切です。もしも赤みや痛みが生じた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
②衣服に付いた場合|水ですすぐ
衣服に電解液が付着した場合も、すぐに水でよくすすいでください。そのまま放置すると布地が腐食し、シミや穴ができる可能性があります。水で落としきれない場合は、中性洗剤を使用して手洗いするのも効果的です。ただし、衣服のダメージがひどい場合は、安全を考慮して廃棄することも検討しましょう。
③家具や床に付いた場合|濡れた布で拭き取る
電解液が家具や床に付着した場合は、濡れた布で丁寧に拭き取ります。表面を傷つけないよう優しく拭くのがポイントです。その後乾いた布で水分を拭き取り、必要に応じて中性洗剤で仕上げ拭きを行います。液漏れを放置すると、木材やプラスチックが腐食する恐れがあるため、早めに対処してください。なお液漏れした場所を掃除した後は、必ず手を洗いましょう。
4.電池の液漏れを防ぐ予防策6選

電池の液漏れを防ぐための6つの予防策をご紹介します。
・新品と古い電池は混ぜて使わない
・長期間使わないときは電池を抜いて保管する
・異なるメーカーや種類を混ぜて使用しない
・定期的に電池の状態を点検する
・高温多湿を避けて保管する
・使用期限を過ぎた電池は使わず処分する
上記のポイントに注意すれば、電池の液漏れを未然に防ぐことが可能です。電池を安全に使うために、これらの対策をしっかり理解しておきましょう。
①新品と古い電池は混ぜて使わない
寿命が異なる電池を同じ機器で使用すると、古い電池に過剰な負荷がかかり、液漏れの原因となります。1〜2か月程度の差であれば問題ない場合もありますが、目安として3か月以上の差がある電池は使用を控えるべきです。
とはいえ、意識していないと電池の使用時期などを覚えている人は少ないでしょう。そこで、使い始めのタイミングで使用開始日をマジックで電池に記載しておくのがおすすめです。使用時期を明確にし、新品と古い電池を混ぜて使わないようにしましょう。
②長期間使わないときは電池を抜いて保管する
電池を長期間機器に入れたままにしておくと、自己放電が進み、液漏れのリスクが高まります。目安として数週間以上機器を使用しない場合は、電池を取り外して保管するようにしましょう。
③異なるメーカーや種類を混ぜて使用しない
異なるメーカーや種類の電池を一緒に使用すると、放電速度や性能にばらつきが生じ、液漏れのリスクが高まります。そのため同じメーカーや種類の電池を使用することが重要です。
「同じ種類」とは、具体的に「アルカリ電池」や「マンガン電池」のことを指します。これらは、それぞれ異なる化学反応で電力を供給しているため、一緒に使用すると片方の電池に過剰な負荷がかかり、液漏れや機器の故障の原因となります。
「同じ電池だから大丈夫」と、種類を気にせず購入したり使ったりすることがありますが、電池にとっては大きな負担となる行為です。必ず同じ種類の電池を組み合わせて使用するようにしましょう。
④定期的に電池の状態を点検する
定期的に機器内の電池を確認し、腐食や液漏れの兆候がないかチェックすることが大切です。もし電池が変色していたり、表面に粉が吹いている場合はすぐに取り外し、新しい電池に交換しましょう。
⑤高温多湿を避けて保管する
電池は高温や湿気に弱く、保管環境が悪いと内部の化学反応が活発になり、液漏れを引き起こすことがあります。そのため、直射日光を避けた涼しく乾燥した場所で保管することが重要です。また密閉容器を使うことで湿気を防げます。電池を安全に保管するために、適切な保管環境を作りましょう。
⑥使用期限を過ぎた電池は使わず処分する
電池の使用期限を過ぎると内部の電解液や電極が劣化し、液漏れのリスクが高まります。そのため使用期限を過ぎた電池は、中身が残っていても使用せずに処分することが大切です。処分の際は自治体のルールを確認し、適切な方法で廃棄するようにしましょう。
このように電池の液漏れを防ぐためには、さまざまな注意が必要です。ほんの少し注意を払うだけで、液漏れを防ぐ可能性がぐっと高まります。電池を安全に長く使うためにも、日々の確認を心がけるようにしましょう。
関連人気記事:乾電池の備蓄は1週間分必要!防災用に選ぶポイントや保管方法も紹介
5.安心して使える!液漏れしない電池3選
「液漏れを予防する対策はわかったけど、いろいろ考えることが多くて面倒…」と感じる人もいるかもしれません。そこでここでは液漏れしない電池を以下3つご紹介します。
・充電式電池
・モバイルバッテリー
・ポータブル電源
これらの機器にはすべて「リチウムイオン電池」が搭載されており、軽量で高いエネルギー密度を持っています。同じサイズの他の電池と比べ、多くの電力を蓄えることができ、繰り返し充電しても劣化しにくいというのがメリット。さらに自己放電が少なく、長期間保管しても電力を保持しやすいのも大きな魅力です。
導入時に費用はかかりますが、充電を繰り返せるため買い替えや廃棄が少なく、コスト面・環境面で優れています。
①充電式電池
充電式電池にも一般的な乾電池と同様に電解液が含まれているため、完全に液漏れしないわけではありません。ただし、アルカリ電池やマンガン電池に比べて液漏れのリスクは非常に低いです。
充電が可能である点を除けば、他の乾電池と使い方は変わらないため、リモコンやおもちゃなど日常的に使用する機器にも簡単に利用できます。充電式電池は3,000円前後で購入でき、手頃な価格で購入しやすいのが特徴。電池の液漏れ予防に適した電力供給機器として、手軽に始められる選択肢です。
②モバイルバッテリー
外出先でスマホやタブレットを充電できるモバイルバッテリーも、液漏れの心配がない電力供給機器です。あらかじめバッテリーを充電しないと使えませんが、持ち運びできいつでも気軽に使えるのが特徴。スマホと同じくらいのサイズのため、カバンに入れても場所を取りません。
外出先でスマホのバッテリーが切れてもすぐに充電できるため、安心して使用を続けられます。Wi-Fiルーターやワイヤレスイヤホンなどを外出先で頻繁に使う人にもおすすめの電力供給機器です。
関連人気記事:モバイルバッテリーを安心して使うには?ケース別の使い方を徹底解説
③ポータブル電源
ポータブル電源はモバイルバッテリーよりも大きな容量を持つポータブル蓄電池です。中には2,000Whもの容量を備え、家中の家電を長時間使用できるモデルもあります。ポート口はUSB以外にAC電源(コンセント)やDCなど、さまざまな種類が搭載されており、異なるデバイスを同時に充電することも可能。暖房器具を使いながらスマホを充電することもできます。さまざまな機器をまとめて充電したい人や、家族が多い人に最適の電力機器です。
関連人気記事:【徹底解説】バッテリー(電池)を長持ちさせるための方法|ポータブル電源
6.災害やアウトドアで活躍するJackeryポータブル電源

ポータブル電源なら「Jackery(ジャクリ)」製品がおすすめです。耐久性に優れた「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用しており、4,000回の充放電が可能。毎日使っても10年以上使用できます。また軽量でコンパクトで持ち運びやすく、アウトドアや災害時など、幅広い場面で活躍できるのも魅力です。さらにJackery(ジャクリ)のポータブル電源は以下のような取り組みにより、高い安全性を確保しています。
・本体の素材に耐久性と放熱性に優れた「ポリカーボネート樹脂とABS(エービーエスアロイ)防火材料」を採用
・BMS(バッテリーマネージメントシステム)でバッテリーの過負荷によるトラブルを防止
・耐衝撃テストで震度7クラスの地震に耐える耐久性を保証
・9メートルの高さから3回落とす落下衝撃試験の実施
・一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品認証」の取得
さらにソーラーパネルとのセット品「Jackery Solar Generator」シリーズなら、太陽光の自然エネルギーを利用した発電も可能。家庭の電気を使わず充電ができるため、節電対策にも効果的です。ポータブル電源を検討している人は、長寿命で持ち運びに便利なJackery(ジャクリ)のポータブル電源を検討してみてください。
関連人気記事:【用途別】ポータブル電源の容量目安|キャンプ・防災で後悔しない選び方
もっと多くの商品を見る
7.電池の液漏れでよくある質問
ここからは電池の液漏れでよくある質問をご紹介します。
●液漏れした電池が原因で火事になることはある?
液漏れした電池は、適切に処理しないと火事の原因になることがあります。特に液漏れした電池が金属などの導電性のある物質と接触すると、ショートして発熱や発火のリスクが高まるため、処分時には十分注意が必要です。ショートを防ぐためには、液漏れ部分をしっかり拭き取り電極部分をテープで絶縁します。その後ビニール袋に個別に入れて自治体の指示に従って適切に処分しましょう。
●電池から液漏れした白い粉がある場合には、どのように掃除したらいい?
電池から液漏れした白い粉がある場合はゴム手袋を着用し、乾いた布やティッシュで表面の粉を慎重に拭き取ります。白い粉は液漏れした電解液が結晶化したものです。触れると皮膚や目に刺激を与える可能性があるため、十分注意してください。掃除後の手洗いも忘れないようにしましょう。
●液漏れした電池を舐めてしまった場合どうしたらいい?
液漏れした電池を誤って舐めてしまった場合、すぐに口を水で十分にすすぎ、吐き出してください。その後冷たい水または牛乳を飲みます。異常があれば速やかに医師に相談しましょう。
参考:家庭に潜む危険物Ⅱ(乾電池、ボタン電池) - 協同組合 藤沢薬業協会
電池の液漏れはアルカリ性または酸性のため、口内や消化器官に刺激を与える恐れがあり大変危険です。放置せず適切な対処を行うことが重要です。
●電池はどのくらいで液漏れする?.
電池の液漏れは、主に長期間放置や過放電が原因です。アルカリ電池やマンガン電池では、数年にわたって使用せず放置すると液漏れのリスクが高まります。
なおアルカリ電池の使用期限は10年間。ただし、未使用でも使用期限を過ぎると液漏れする可能性は高まるため、早めに使うことも大切です。
まとめ
電池が液漏れした場合、以下の手順で速やかに対応することが大切です。
・ゴム手袋を着用して乾いた布やティッシュで拭き取る
・電池は端子部分をテープで絶縁しビニール袋に入れる
・自治体の指示に従った方法で処分する
液漏れを放置すると機器が損傷し、使用不能になる恐れがあります。早めに対応しましょう。「液漏れしない電池はないの?」と思う人には以下の3つがおすすめです。
・充電式電池
・モバイルバッテリー
・ポータブル電池
どれも導入には費用がかかりますが、繰り返し充電できるため、買い替えの手間やコストを抑えることができます。次の電力供給機器を検討する際は、上記の製品を選択肢に入れてみてください。
特にポータブル電源は、大容量バッテリーでありながら持ち運びができ、多用途に使える点で非常に便利です。ポータブル電源を検討する際は、ぜひJackery(ジャクリ)の製品もチェックしてみてください。
























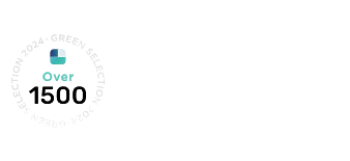




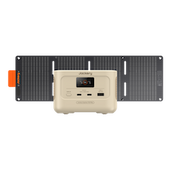



























































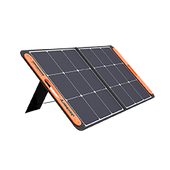
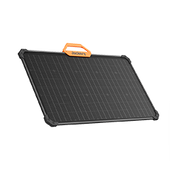
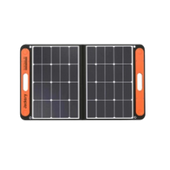














































コメント